「夏は涼しく、秋は紅葉を楽しみたい」…
そんな願いを叶えるのが落葉樹。
この記事では、常緑樹との違い、メリット、初心者でも失敗しない植え方・育て方、おすすめ品種までをやさしく解説していきます。

落葉樹は季節の変化を感じることが出来ます。ぜひ参考にしてください。
落葉樹とは?常緑樹との違いをサクッと整理
庭木を選ぶときに必ず迷うのが「落葉樹」と「常緑樹」。
どちらも魅力がありますが、特徴や役割は大きく異なります。とくに、落葉樹は四季の変化を感じられる一方、常緑樹は一年中緑を楽しめるのが強み。
ここでは、落葉樹とはどんな樹木なのか、常緑樹との違いをわかりやすく整理し、暮らしに合った庭木選びのヒントをお伝えしていきます。
落葉樹とは
落葉樹は秋から冬にかけて葉を落とし、春に再び芽吹く樹木のことです。
そのため、四季の変化を感じやすく、日本の庭や街並みに季節感を与えてくれます。とくに、代表的な落葉樹には、モミジ・サクラ・イチョウ・ハナミズキ・ケヤキなどがあります。
暮らしに役立つポイント
落葉樹は「夏と冬で役割が変わる」点が大きな魅力です。
夏
- 葉が茂り、強い日差しをやわらげてくれる
- 室内の温度上昇を防ぎ、省エネ効果
冬
- 葉が落ちて光を通す
- 日差しが室内に届き、暖かく快適に過ごせる
つまり、自然の力を利用して省エネ&快適性を同時にかなえてくれるのです。
常緑樹との違い
常緑樹は名前のとおり一年中葉がついている樹木です。
そのため、冬でも緑を楽しめ、目隠しや防風・防音の役割を担います。ただし、季節による光や風のコントロールには落葉樹ほど柔軟ではありません。
迷ったら比較から
庭木を選ぶときは、まず「どんな暮らしを優先したいか」を考えるのがおすすめです。
- 四季の変化を楽しみたい → 落葉樹
- 年中緑を保ち、目隠しや防犯を重視 → 常緑樹
なぜ落葉する?:自然のしくみと役割
「秋になると木々が一斉に葉を落とすのはなぜだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。実は落葉は、木が冬を生き抜くための大切な知恵なのです。
乾燥・凍結に備える
冬は気温が下がり、土の水分も凍結しやすくなります。
そのため、その状態で葉を残したままだと、葉からどんどん水分が蒸発してしまい、幹や根が乾燥して枯れてしまうリスクがあります。
そこで木は、あえて葉を落とすことで水分の消耗を最小限に抑え、自らを守っているのです。
積雪対策
雪が積もる地域では、葉があるとその重みで枝が折れる危険があります。そのため、葉を落とすことで雪が積もりにくくなり、枝折れや幹へのダメージを防ぐ役割を果たしています。
これは、自然がつくり出した「雪国対策」ともいえる仕組みです。
土づくりへの貢献
落ち葉は地面に落ちるとやがて分解され、腐葉土となって土壌に栄養を与えます。
つまり、落葉は単なる「不要物の処分」ではなく、次の春に向けて植物や微生物の命をつなぐ栄養循環の一部なのです。
👉 このように、落葉は「木自身を守るため」と同時に「森や庭の生態系を豊かにするため」の二重の役割を持っています。
落葉樹の5つのメリット
落葉樹は、ただ四季で姿を変えるだけの樹木ではありません。実は、暮らしを快適にし、家や庭の価値を高める多くのメリットを持っています。
とくに、夏は涼しさを生み出し、秋は彩りを添え、冬は光を届ける…
そんな自然のサイクルが私たちの生活に役立っているのです。
ここでは、落葉樹を庭に取り入れることで得られる5つの魅力をわかりやすくご紹介していきます。
1. 夏の日差しを遮る“自然のカーテン”
落葉樹は夏になると青々とした葉を茂らせ、直射日光をやわらげます。
とくに、葉の蒸散作用により周囲の温度を下げる効果もあるため、庭や室内が涼しく感じられ、冷房効率もアップ。
夏の庭づくりヒント
- ウッドデッキや窓の近くに落葉樹を植えると、木陰が自然のオーニングとなり、猛暑対策につながります。
2. 秋は“天然のアートギャラリー”
紅葉のシーズンになると、赤や黄色に染まる落葉樹はまるで絵画のような美しさ。これにより、季節の移ろいを肌で感じられるだけでなく、視覚的なリラックス効果も期待できます。
秋の楽しみ方
- 庭にススキや秋咲きの花を組み合わせれば、よりドラマチックな秋の風景が楽しめます。
3. 空気清浄効果で暮らしを快適に
落葉樹は光合成で二酸化炭素を吸収し、酸素を生み出すだけでなく、葉が空気中のホコリや微粒子をキャッチしてくれます。
そのため、庭に一本あるだけでも、周辺の空気がやわらかく感じられるのはそのためです。
4. 雨風から住まいを守る
枝葉があることで、雨や風の衝撃をやわらげ、家の外壁や窓への直撃を防いでくれます。これにより、外壁の劣化スピードを抑え、住まいを長持ちさせる効果も。
このように、庭木が“天然のバリア”になってくれるのです。
5. 景観価値の向上
春の新緑、夏の木陰、秋の紅葉、冬の枝ぶり…
落葉樹は四季ごとに異なる表情を見せ、外観を豊かに彩ります。そして、家の印象を高めるだけでなく、日々の暮らしに「季節を楽しむ満足感」を与えてくれます。
シンボルツリー選び
- モミジやハナミズキは季節の変化がわかりやすく、庭のアクセントにおすすめです。
庭木におすすめの落葉樹3選
庭に一本植えるだけで雰囲気がガラッと変わるのが落葉樹。
ここでは、成長が穏やかで手入れも少なく、初めての庭木として取り入れやすい3種をご紹介していきます。
ハナミズキ
見どころ
- 春の華やかな花(総苞)+秋の赤い実
紅葉
- ○
樹高目安
- 3〜6m
手入れのしやすさ
- 成長緩やかで剪定は少なめ。庭のシンボルに◎
イロハモミジ
見どころ
- 繊細な葉と和の趣。
- 紅葉は圧巻
紅葉
- ◎(赤〜橙)
樹高目安
- 3〜5m
手入れのしやすさ
- 病害虫に比較的強く、管理しやすい
アオダモ
見どころ
- 春の白い小花と軽やかな樹形
紅葉
- ○(黄葉)
樹高目安
- 2〜6m
手入れのしやすさ
- 自然な樹形を保つため剪定は最小限でOK
苗の選び方のコツ
初心者でも失敗しにくい苗選びのポイントは次の3つ。
- 根鉢がしっかり締まっている・・・健康な根が育ちやすい
- 幹がまっすぐ立っている・・・成長後も見映えが良い
- 接ぎ口が健全(ぐらつきや傷がない)・・・成長が安定
この3点を意識するだけで、長く元気に育つ樹木を選びやすくなります。
ワンポイントアドバイス
- 「庭の主役にしたい」なら花や紅葉が華やかなハナミズキやイロハモミジ
- 「ナチュラルな雰囲気が好き」なら軽やかな枝ぶりのアオダモ
植え方ガイド(休眠期に安全・確実)
落葉樹を植えるベストシーズンは11〜3月の休眠期。
なぜなら、葉が落ちて活動が止まっているため、植え替えによるダメージが少なく、根が安定しやすい時期だからです。
そのため、初心者でも安心して挑戦できます。
ステップ手順
1.植穴を根鉢の1.5〜2倍掘る
- 広めに掘ることで根が伸びやすくなり、活着がスムーズに。
2.掘り土に腐葉土・堆肥を混ぜて土壌改良
- 水はけと保水性のバランスを整え、根の発育をサポート。
3.深植えNG
- 地表と元の用土面を合わせる
- 深すぎると根腐れ、浅すぎると乾燥の原因に。
- 水平を意識して調整。
4.根元を軽く踏み固め、たっぷり潅水
- 空気を抜いて根と土を密着させ、水で落ち着かせる。
- 初回の水やりは特に重要。
5.風対策に支柱を設置(八の字結び)
- 強風で根が揺れると定着が遅れるため、支柱でしっかり固定。
- 八の字結びにすると幹を傷めにくい。
置き場所の目安
日当たり&風通し良好
- 光合成がしっかりでき、病害虫にも強くなる。
排水性のある土壌
- 水はけの悪い場所では根腐れしやすいので、砂利や腐葉土で改良しておくと安心。
建物・塀から1〜2m離す
- 将来の根の広がりや枝の張りを見越して余裕を確保。
- 家の外壁や隣家とのトラブル防止にも。
ワンポイントアドバイス
- 植え付け後の最初の1年は特に水やりを欠かさないことが成功のカギ。
- マルチング(バークチップや落ち葉)を根元に敷けば、乾燥防止&見た目アップ。
育て方の基本(年間メンテの要点)
落葉樹は四季を通して姿を変えるため、時期に合わせたケアが大切です。
とく、難しい専門技術は必要ありませんが、「水やり・肥料・剪定・病害虫対策」の4つを押さえることで、健康で美しい樹形を保てます。
水やり
植え付け後〜活着まで
- 表土が乾いたらたっぷり与えるのが基本。
- まだ根が浅いため、乾燥させないよう注意。
真夏
- 朝か夕方に水やりをすると蒸発が抑えられ、効率的に吸収されます。
- 昼間の水やりは根を傷める原因になることも。
休眠期(冬)
- 樹木の活動が止まるため、水やりは控えめにして根腐れを防ぎます。
時短の工夫
- 自動水やり器やタイマーを使うと、旅行や忙しい日も安心です。
肥料
落葉樹は肥料を欲しがるタイミングが決まっています。
- 寒肥(11月頃)・・・冬の間にゆっくり効き、春の成長に備える。
- 芽出し前(2〜3月)・・・新芽や花芽を支えるための追肥。
緩効性の有機肥料を株元にまき、土と軽く混ぜ込みます。しかし、与えすぎると枝が伸びすぎたり病害虫を呼ぶ原因になるので「控えめ」が鉄則。
剪定
適期
- 休眠期(12〜2月)。
- 葉がないため枝ぶりがよく見え、樹木への負担も少ない。
内容
- 枯れ枝、交差してこすれ合う枝、混み合って風通しを悪くしている枝を整理。
ポイント
- シルエットを整えるよりも「自然な樹形を活かす」程度にとどめるのが初心者向け。
👉 剪定が不安な場合はプロに依頼するのも安心です。
病害虫対策
落葉樹は病害虫に強い種類も多いですが、油断は禁物です。
日常ケア
- 落ち葉を溜め込まず、風通しを良くする。
- これだけでも害虫やカビを減らせます。
初期対応
- 異常な葉(斑点や食害)は早めに除去。
- 被害が広がる前に予防散布やピンポイントの薬剤処理を。
👉 自分の手に負えないときは、プロに害虫駆除を任せることも1つの手です。
よくある質問(FAQ)
落葉樹を植えてみたいと思っても、「狭い庭でも大丈夫?」「落ち葉掃除は大変そう…」
と不安に感じる方は多いものです。
そこでここでは、初心者がよく抱く疑問とその解決策をQ&A形式でわかりやすくまとめました。そして、実際に育てるイメージをふくらませながら、不安をひとつずつ解消していきましょう。
Q1. 小さな庭でも落葉樹は植えられる?
A. はい、可能です。
落葉樹は大木になるイメージがありますが、樹高3〜4m程度で成長がゆるやかな品種を選べば小さな庭でも楽しめます。
例えば、ハナミズキやアオダモの矮性種はコンパクトで扱いやすく、庭のシンボルツリーにぴったり。
また、建物や塀から最低1m以上離して植えると、将来の根や枝の広がりにも安心です。
Q2. 落ち葉掃除が不安…
A. 実はそれほど大変ではありません。
落ち葉が集中するのは秋〜初冬の短い期間だけ。そのため、毎日のように落ち葉が出るわけではなく、1シーズンに数回の掃き掃除で十分です。
さらに、工夫を加えればラクになります。
例えば、防草シート+バークチップを敷くと落ち葉が掃きやすくなり、掃除時間が大幅に短縮。そして、集めた落ち葉は堆肥にして再利用することで、土壌改良材として庭に還せるので一石二鳥です。
Q3. 西日が強い場所は?
A. 品種選びと乾燥対策で解決できます。
西日が強い場所は乾燥や葉焼けのリスクがありますが、西日耐性や半日陰でも育つ樹種(アオダモや一部のモミジなど)を選べば安心。
加えて、株元にマルチング(腐葉土やウッドチップ)を施すことで土の乾燥を防げます。また、真夏は夕方にしっかり潅水しておくと、日中のストレスを和らげられます。
Q4. 植え付け直後に元気がない…
A. ほとんどの場合「根がまだ馴染んでいない」ことが原因です。
新しく植えた樹木は根が十分に広がっていないため、少し元気がないように見えることがあります。とくに、水切れは大敵なので、朝のうちにたっぷり潅水してあげましょう。
さらに、株元にマルチ材を敷いて水分を保ち、強い日差しが続くときは簡易シェードで日よけをすると回復しやすくなります。
まとめ:落葉樹で“季節が巡る庭”をつくろう
いかがでしたか?
要点
- 落葉樹は夏は涼しく、冬は暖かい住環境をつくる天然のサポーター
- 紅葉・若葉・花・枝ぶりと、四季折々の景観を楽しめる
- 植え付けは休眠期(11〜3月)が安全。深植えNG+支柱設置+たっぷり潅水が基本
- 肥料は「寒肥+芽出し前」の2回、剪定は休眠期に最小限で自然樹形を活かす
今日からできる行動
- 庭の日照やスペースをチェック(建物から1〜2m離せるか確認)
- 候補の樹種を2種類に絞る(例:イロハモミジで紅葉を楽しむ/ハナミズキで花を楽しむ)
- 次の週末に必要な資材を用意(苗・腐葉土・支柱・マルチ材など)
まずは1本からで大丈夫です。
落葉樹は「季節を運んでくれる庭木」。そして、あなたの庭にも四季の彩りと快適さを迎え入れてみませんか?
関連記事:
- 【ガーデニング初心者必見!】ガーデニングを始める前に知っておきたい基本のキホン
- 【初心者向け】シンボルツリーを選ぶ時の注意点
- ガーデニングの魅力と効果とは?初心者向け始め方ガイド
- 【庭づくりで心をリフレッシュ!】ガーデニングでリラックス
- 【初心者向け】おしゃれな庭に欠かせない!庭木の選び方と配置のコツ
- 【植物が元気ない?】活力液で蘇らせよう!
- 【庭木の剪定は自分でできる!】 初心者でも失敗しないコツ
- 【庭木剪定の極意をマスター】プロの技術で庭を変える「剪定教室」
- 【初心者におすすめの庭木剪定ツール】選び方から使い方まで完全ガイド!
- お庭のメンテナンスが簡単に!【お庭110番】の魅力
- 【庭を彩る紅葉低木】四季折々の美しさを楽しむためのガイド
- ニームオイル配合「バイオアクト-TS」の効果と使い方
- 【全国対応剪定110番!】庭木の剪定をプロがスピード解決
- 【初心者向け!】地植えで始めるガーデニングの基本とコツ
- 【初心者向けガーデニングガイド!】庭作りの基本とおすすめ植物

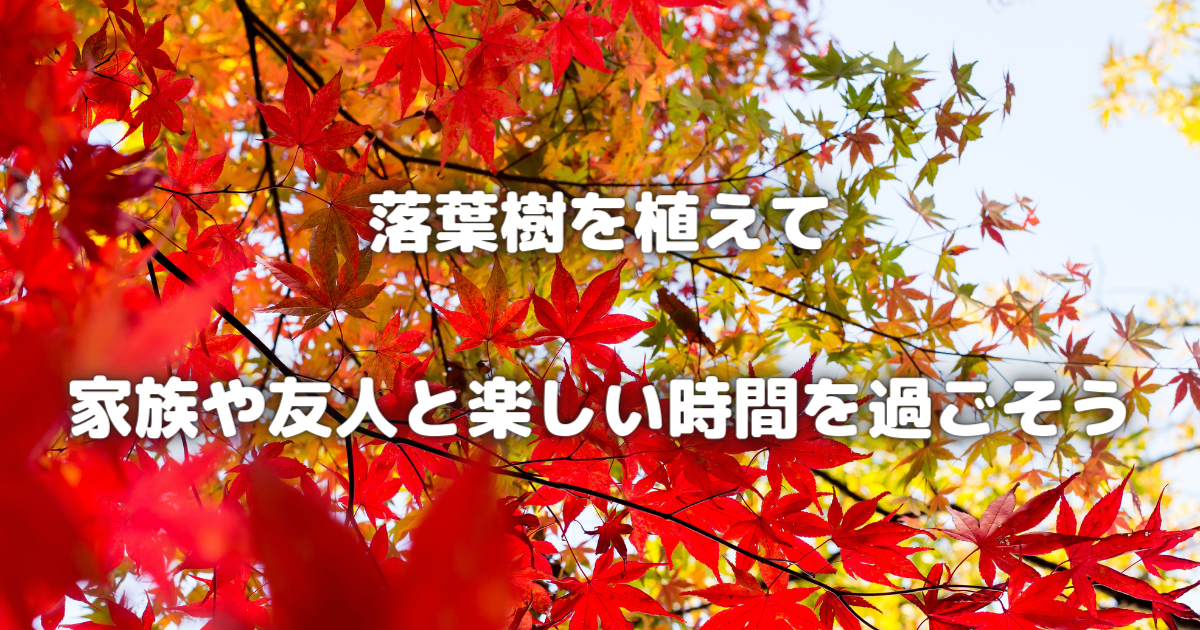















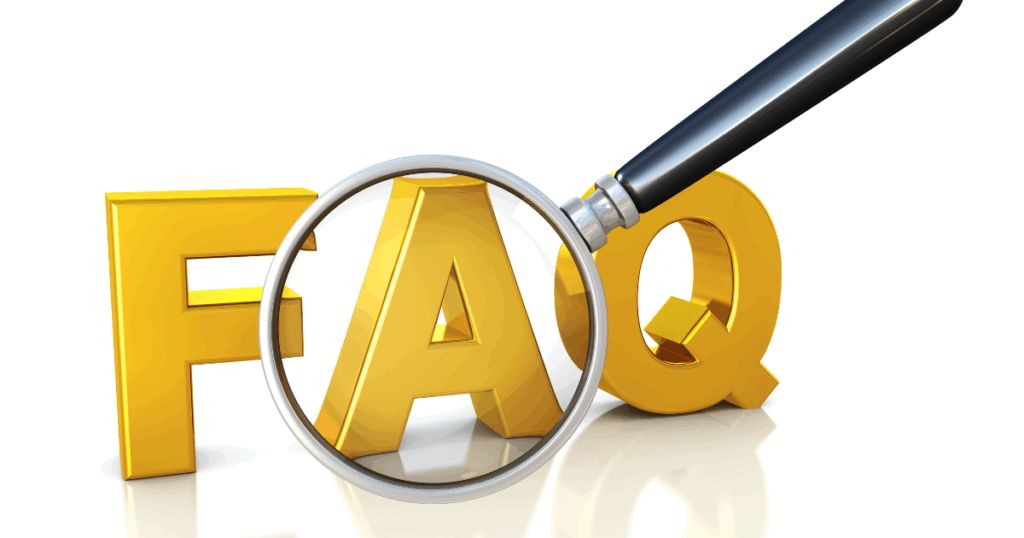
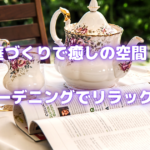

コメント