春先、枝いっぱいに小さな白花を咲かせ“雪景色”のように庭を彩るユキヤナギ(雪柳)。
丈夫で環境への適応力が高く、初心者でも育てやすい落葉低木です。そして、成功のポイントは、適期に植える・排水のよい用土・花後の剪定。
この記事では、植え付けから日常管理、剪定・挿し木、季節ごとのケア、庭での活用までをステップ順にわかりやすく解説していきます。

庭に取り入れることで四季の変化を楽しめるユキヤナギの魅力を、ぜひあなたのガーデニングに活かしてみませんか?
ユキヤナギの基礎知識(特徴・耐性・日当たり)
ユキヤナギは、春の訪れを告げる代表的な花木で、枝いっぱいに小さな白い花を咲かせる姿から「雪が降り積もったように見える」とも言われています。
そして、しなやかな枝が弓なりに垂れ下がる樹形は、和風・洋風どちらの庭にも自然に溶け込み、植えるだけで庭の雰囲気を華やかに演出してくれます。
- 学名:Spiraea thunbergii(バラ科シモツケ属)
- 原産:日本・中国
- 樹高:1〜2m(しなやかな枝垂れ状の樹形)
- 開花:3〜4月(早春〜春本番)
- 耐性:耐寒・耐暑ともに強い
日当たり
- 日向が理想的で、十分な日差しがあると花付きがよくなります。
- 半日陰でも育ちますが、花数はやや減少。
- 庭の南側や東側など、明るい場所に植えると最も美しい姿を楽しめます。
水やりのポイント
- 地植え・・・根付いたあとは雨任せでも大丈夫。極端に乾燥した時期のみ水やりすればOK。
- 鉢植え・・・乾きやすいので水切れ注意。土の表面が乾いたらたっぷり与えるのが基本。
👉 とくに、鉢植えの場合は「水やりタイミングを見極める力」が、美しい花を長く楽しむコツになります。
ワンポイント豆知識
- ユキヤナギの花言葉は「愛らしさ」「気まま」。可憐な花姿にぴったりの意味です。
- 枝を切って花瓶に生けても長持ちするので、庭と室内の両方で楽しめます。
- 庭に取り入れることで、春の季節感を一気に引き立てる主役級の存在になります。
このように、ユキヤナギは「丈夫・育てやすい・華やか」という三拍子が揃った優秀な花木です。そのため、日当たりと水やりの基本を押さえることで、初心者でも失敗なく春の景色を楽しむことができます。
ユキヤナギの植え付けのコツ(時期・場所・用土・手順)
ユキヤナギは「植え付けのタイミング」と「環境づくり」を押さえることで、初心者でも失敗しにくい花木です。ここでは、元気に育てるための具体的なポイントをわかりやすく解説していきます。
適した時期
秋(10〜11月)
秋は気温が安定しており、植え付け後に根がじっくり張りやすい時期です。
なぜなら、冬の間に根が落ち着くからです。そのため、翌春には花付きが良くなりやすく、初心者にとっては最もおすすめのタイミングです。
春(2〜3月)
冬の寒さが厳しい地域では、春の植え付けが安心。なぜなら、成長期直前に植えることで、根が活動を始め、スムーズに定着してくれるからです。
👉 まとめると、温暖地は秋植え、寒冷地は春植えがベストです。
場所の選び方
日当たりと風通しの良さが重要
ユキヤナギは花付きに日光が欠かせません。とくに、午前中にしっかり日が当たる場所なら、花数も増えて見応えがアップします。
水はけの悪い場所は避ける
過湿は根腐れの原因。粘土質の土なら砂利や川砂を混ぜて排水性を改善しましょう。また、雨水がたまりやすい低地では、やや高めの位置に植えると安心です。
用土の目安
市販の庭木・花木用培養土で十分OK
初心者は迷わずこれで大丈夫。なぜなら、保水性・排水性・通気性のバランスが良いからです。これにより、ユキヤナギの根も伸びやすい環境になります。
自作配合の場合
- 赤玉土(中粒)6:腐葉土3:川砂1
- 水はけと保水を両立できる黄金比率。
鉢植えの場合
- 鉢底に鉢底石を敷く
- 土はやや軽めの配合にして排水性を高める
👉 鉢植えでは特に乾燥しやすいので、土が軽すぎないよう赤玉土多めを意識すると良いです。
植え付け手順
1.植え穴を掘る
- 根鉢の直径の約2倍、深さは根鉢と同じくらいを目安に掘ります。
- 広さを確保することで、根が伸びやすくなります。
2.掘り土に腐葉土+元肥を混ぜる
- 緩効性肥料を少量混ぜ、土をふかふかに整えるのがコツ。
- これで植え付け直後の根張りがスムーズに。
3.根鉢を軽くほぐす
- ポットから外したら、根の表面を少しほぐしてあげます。
- 根が絡まっている場合は軽く広げると、新しい土に伸びやすくなります。
4.植える高さを調整
- 地際が周囲の地面と同じ高さになるように植えます。
- 深植えすると蒸れて弱りやすいので注意。
5.たっぷり灌水する
- 植え付け直後は、水をたっぷり与えて土と根を密着させましょう。
- 根の空気ポケットをなくすことで、活着率が上がります。
6.マルチングで仕上げ
- 根元にバークチップやワラを敷くと、乾燥防止・泥はね防止に効果的。
- 見た目もナチュラルに仕上がります。
ワンポイントアドバイス
- 植え付け後1〜2週間は乾燥させないことが最優先。
- 風が強い場所では支柱を立てて倒伏防止。
- 鉢植えは1〜2年ごとに植え替えると根詰まり防止になり、花付きも安定します。
ユキヤナギの水やり・肥料の年間ルーティン
ユキヤナギはとても丈夫な花木ですが、「水やり」と「肥料」のリズムを押さえることで、花付きや樹形の美しさがぐっとアップします。
基本は「与えすぎない」こと。また、少なすぎても多すぎてもトラブルの原因になるので、年間を通じたメリハリのある管理が大切です。
水やりのポイント
地植えの場合
- 植え付け直後は根がまだ安定していないので、土が乾いたらたっぷり水を与えます。
- 根付いてからは基本的に“雨任せ”でOK。自然降雨だけで十分育ちます。
- ただし、真夏に雨が降らず乾燥が続くときは要注意。夕方や早朝に補助的に水やりをしてあげましょう。
鉢植えの場合
- 鉢は地植えよりも乾きやすいため、土の表面が乾いたらすぐに水やり。
- 与えるときは鉢底から水が流れ出るまでしっかり行うのが鉄則。根全体に水分が届き、根腐れも防ぎやすくなります。
- 夏は特に蒸発が早いため、朝と夕方の涼しい時間帯に与えるのがおすすめです。昼間の高温時は避けると、根へのダメージが少なくなります。
👉 ポイントは 「乾いたらたっぷり、常に湿らせっぱなしにしない」 ことです。
肥料の与え方
寒肥(1〜2月)
- 花芽をつけるための大切な栄養補給の時期。
- 根元から少し離れた位置に、緩効性肥料を控えめに施します。
- 寒肥をしっかり与えると、春の花付きが見事になります。
お礼肥(花後・5月頃)
- 開花で消耗した株を回復させるための栄養補給。
- 緩効性肥料や有機肥料を軽く与えると、枝葉の充実につながります。
- 与えすぎると枝が徒長(ひょろひょろ伸びすぎ)するので注意。
鉢植えの場合
- 地植えに比べて養分が流れやすいため、春〜秋の成長期に月1回程度の追肥がおすすめ。
- 液体肥料を薄めて与える方法も効果的で、即効性があるので生育を安定させられます。
👉 肥料は「少なめ」が基本。過肥は病害虫を招きやすく、枝葉ばかり茂って花付きが悪くなる原因にもなるので注意しましょう。
ワンポイントアドバイス
- 肥料は「株元から少し離して」与えると、根を傷めにくく安全。
- 水やりと肥料はセットで考え、乾いた土に肥料を置き、その後しっかり水をかけると効果が高まります。
- 年間を通じて「控えめ・適量」を意識することで、花も葉もバランスよく育ちます。
ユキヤナギの管理は、基本的に「ほったらかし気味」でも大丈夫ですが、水やりと肥料のルーティンを少し意識するだけで、春の花姿が見違えるほど豪華になります。
とくに、鉢植えの場合は水やりと肥料切れに注意し、季節ごとに必要なケアをしてあげることが大切です。
ユキヤナギの花を増やす剪定のコツ
ユキヤナギは「花の多さ」が大きな魅力です。しかし、そのためには正しい剪定のタイミングと方法が欠かせません。なぜなら、ユキヤナギは、春に伸びた新しい枝の先端に翌年の花芽を作る性質を持っているからです。
そのため、剪定の時期を間違えると、せっかくの花芽を切り落としてしまい、翌年の花付きが悪くなってしまうのです。
剪定のタイミング
花後すぐ(4〜6月)
- 花が咲き終わった直後に行うのがベスト。
- 遅れると花芽が形成されてしまい、翌春の花を減らしてしまいます。
冬(12〜2月)
- 冬はあくまで「軽い整理」だけ。
- 枯れ枝や絡んだ枝を取り除く程度にとどめ、強剪定は避けましょう。
👉 鉄則:花を増やしたいなら「花後すぐ剪定」!
花後の基本手順
外へ飛び出す枝を切り戻す
- 樹形から大きくはみ出た枝は、枝の分かれ目や節の上で軽く切ると自然なまとまりが出ます。
古枝(3〜4年枝)の更新
- 花付きが悪くなった古い枝は、根元から切って更新。
- 新しい枝に世代交代させることで、株全体が若返り、毎年フレッシュな花を楽しめます。
込み合う部分を間引く
- 枝が密集すると、風通しや日当たりが悪くなり病害虫の原因に。
- 内向きの枝や交差している枝を間引くと、花芽がつきやすくなります。
剪定のポイントと注意点
「毎年少しずつ」更新が理想
- 一度に強く切り戻すと株が弱るので、古枝は少しずつ入れ替えていくのがコツ。
切り口は斜めに
- 雨水が溜まらないように、枝の上部を斜めにカットすると病気予防になります。
切り戻しは“軽く”
- 深く切りすぎると花芽を落としてしまうため、花後は“整える程度”を意識しましょう。
ワンポイントアドバイス
- 剪定後は株元に腐葉土や堆肥を軽くすき込むと、新しい枝の伸びが良くなります。
- 花後の剪定を毎年習慣にすれば、樹形を乱さず花付きも安定。初心者でも失敗しにくい管理法です。
- 冬に強剪定したくなる人も多いですが、ユキヤナギは冬剪定=花芽を切ると覚えておくと安心です。
このように、ユキヤナギを毎年豪華に咲かせたいなら、「花後すぐ」の剪定と、冬は軽い整理を徹底することがポイントです。
そして、古枝を少しずつ更新しながら風通しの良い株を維持することで、毎年ボリューム満点の花姿を楽しめます。
また、剪定に自信のない方は、プロに任せるという選択肢もあります。
そして、プロに任せるなら、「剪定110番」がおすすめです。
ユキヤナギの病害虫対策(うどんこ病/アブラムシ)
ユキヤナギは丈夫で管理しやすい花木ですが、油断すると「うどんこ病」と「アブラムシ」に悩まされることがあります。
また、どちらも発生しやすい環境や時期があるため、予防と早期対応を心がけることが、健康な株を長く保つ秘訣です。
うどんこ病
症状
葉の表面に白い粉をまぶしたような斑点が広がり、進行すると葉が変形したり、生育が弱まります。とくに、枝葉が込み合い、湿気がこもる環境で発生しやすい病気です。
予防法
- 間引き剪定で風通しを良くする
- 内側に伸びた枝や交差枝を切ることで、風が通りやすくなり病気を防げます。
- 過剰な肥料を避ける
- とくに、チッ素肥料を与えすぎると葉が茂りすぎて蒸れやすく、病気の温床に。
- 肥料は「控えめ」が基本です。
対処法
- 発症した葉は早めに摘み取って処分し、病気の広がりを防ぐ。
- 被害が広がるようなら、ベンレートやダコニールなどの適用薬剤をローテーションで散布。
- 連用を避けることで耐性菌の発生を防げます。
アブラムシ
症状
春先の柔らかい新芽に群がり、汁を吸って株を弱らせます。また、放置すると葉が縮れ、すす病の原因になることもあります。
初期対応
- 少数であれば、水流で洗い流すのが効果的。
- ホースのシャワーで葉裏を中心に洗い流すと簡単に落ちます。
- ガムテープを軽く押し当てて、物理的に取り除く方法も。
- 薬剤に頼らず済むので安心です。
増加時の対応
- 数が増えすぎた場合は、アセフェート剤・マラソン乳剤などの適用殺虫剤を規定濃度でスポット散布。
- 散布は風のない日を選び、蕾や花弁を避けて葉や枝を中心に行いましょう。
病害虫対策のワンポイント
- 「予防7割・対処3割」を意識すると失敗が少なくなります。
- 株元を清潔に保ち、枯葉や落ち葉を放置しないことも病害虫予防につながります。
- アブラムシは天敵(テントウムシなど)が発生すると自然に減ることもあるので、薬剤は「どうしても必要なとき」に限りましょう。
このように、ユキヤナギは基本的に手間のかからない花木ですが、風通しを良くし、栄養過多を避けることで病害虫を未然に防げます。
また、うどんこ病もアブラムシも、「早めの気づきと軽い処置」が何より効果的。そして、日々の観察を習慣にして、健康で花付きの良い株を育てましょう。
ユキヤナギの増やし方:挿し木と株分け
ユキヤナギは成長が早く、丈夫な性質を持つため「挿し木」と「株分け」で簡単に増やせる花木です。
そのため、園芸初心者でも挑戦しやすく、お気に入りの株をたくさん育てて庭や鉢で楽しむことができるのが魅力です。
ここでは、それぞれの方法を詳しく解説していきます。
挿し木(初心者にもおすすめの方法)
ユキヤナギを増やすなら、挿し木がもっとも成功率の高い方法です。
適期
- 3月(芽吹き前)・・・
まだ新芽が動き出す前なので、枝がしっかりしており発根しやすい。 - 6〜7月(梅雨どき)・・・
湿度が高く発根が促進されやすい。真夏の強光を避ければ高確率で成功します。
手順
- 今年伸びた10〜15cmの若枝をカット。下葉を取り除き、先端は斜めに切って水分を吸いやすくする。
- 切り口を水に数分浸けて「水揚げ」を行い、余裕があれば発根促進剤(ルートンなど)を薄く塗布。
- 清潔な挿し木用土(赤玉小粒、鹿沼土、バーミキュライトなど)に枝を半分ほど挿し込む。
- 明るい日陰で高湿度を保ち管理。乾燥を防ぐために透明なビニールカバーや発泡容器を併用すると効果的。
- 2〜3週間ほどで発根が確認できたら、鉢上げして通常管理に切り替えます。
👉 挿し木は、「清潔な土」「乾燥させない環境」が成功のカギ。
株分け(株が大きくなったらチャレンジ)
大株に育ったユキヤナギは、株分けでも簡単に増やせます。そして、挿し木より手間はかかりますが、確実に成長株を得られる方法です。
適期
- 2〜3月(芽吹き前)
- 10〜11月(植え替えシーズン)
- 活動期の直前・直後が株への負担が少なくおすすめ。
方法
- 株全体をスコップで掘り上げる。
- 根を傷めないように注意しながら、数本ずつまとまるように分ける。
- 分けた株を通常の植え付け手順に従って植え戻す。植え穴には腐葉土や元肥を混ぜて、活着を助けます。
👉 株分けは古い株のリフレッシュにもなるため、一石二鳥の方法です。
ワンポイントアドバイス
- 挿し木・株分けともに、作業後はたっぷり灌水して根と土を密着させることが大切。
- 植え付け後1〜2週間は直射日光を避け、半日陰で管理すると失敗が少なくなります。
- 増やした株は庭植えや鉢植えのほか、花壇の縁取りや生垣としても活躍します。
このように、ユキヤナギは「挿し木」で気軽に、「株分け」で確実に増やせる丈夫な花木。
そして、いずれの方法も初心者が挑戦しやすく、一株から庭中に広がるユキヤナギの雪景色を楽しむことも夢ではありません。
ユキヤナギの季節ごとの管理チェック表
ユキヤナギは丈夫で育てやすい花木ですが、季節ごとの管理ポイントを押さえると花数が増え、株姿も美しく整います。では、春から冬までの流れを見ていきましょう。
春(3〜5月):開花〜花後ケアが勝負
開花鑑賞
- 3月〜4月に満開を迎え、枝いっぱいに雪のような花を咲かせます。
- この時期は株の姿を存分に楽しみましょう。
花後すぐの剪定(4〜6月)
- 翌年の花芽は春の新梢に作られるため、花後すぐの剪定が鉄則。
- 外に飛び出した枝や古枝を整理して、株全体を若返らせます。
お礼肥(5月頃)
- 開花で消耗した株を回復させるために、緩効性肥料を軽めに施すと、その後の新梢がしっかり伸びて翌年の花付きも良くなります。
夏(6〜8月):乾燥と蒸れに注意
乾燥対策
- 真夏は乾燥で葉が傷みやすい時期。
- 根元をバークチップやワラでマルチングすると、乾燥防止と泥はね予防になります。
水やり
- 鉢植えは特に乾きやすいので、朝夕の涼しい時間帯に灌水。
- 真昼の水やりは蒸れや根傷みの原因になるので避けましょう。
徒長枝の軽整枝
- 花後に伸びた徒長枝が姿を乱す場合は、樹形を整える程度に軽くカット。
- 強い切り戻しは来年の花芽を減らすので注意。
秋(9〜11月):植え付け&株分けに最適
植え付け適期
- 秋は気温が安定し、根がしっかり張りやすいため、ユキヤナギを植えるのに理想的な季節です。
- 翌春の開花にも好影響。
株分け
- 大株になった場合は、株を掘り上げて数本ごとに分け、植え直すことでリフレッシュ&増殖が可能です。
肥料で冬支度
- 緩効性肥料を軽めに施し、冬に備えて株を充実させておきましょう。
冬(12〜2月):休眠期の整理
寒肥
- 1〜2月に緩効性肥料を根元から少し離して与えると、春の芽出しと花付きが良くなります。
病枝・枯枝の除去
- 冬の間は枝の状態がよく見えるので、病気の枝や枯れ枝を取り除くのに最適。
- 株を清潔に保つことで春の生育がスムーズに。
強剪定は避ける
- 冬に大きく切り戻すと花芽を落としてしまいます。
- あくまで“整理剪定”に留めるのがポイントです。
このように、ユキヤナギは「春に楽しみ、夏に守り、秋に仕込み、冬に整える」流れで管理することで、毎年ボリューム満点の花姿を楽しめます。
そのため、季節ごとのメリハリあるケアを意識することで、初心者でも失敗なく美しい株に育てられます。
庭づくりでのユキヤナギ活用アイデア(寄せ植え・和風・生垣)
ユキヤナギはしなやかな枝と雪のように咲き誇る白花が魅力。
そのため、単体で植えても見栄えしますが、組み合わせや配置次第で庭の雰囲気を格段に引き上げることができます。
ここでは、「寄せ植え」「和風」「生垣」など、シーン別の活用法を詳しくご紹介していきます。
春の寄せ植えで“絵になる花壇”に
ユキヤナギの純白の花は、春の花壇における引き立て役にも主役にもなる存在です。
おすすめの組み合わせ
- チューリップ・・・赤・ピンク系を合わせると華やかさ倍増。
- ムスカリ・・・青紫とのコントラストが白花をより際立たせます。
- パンジーやビオラ・・・足元に色を添えると、立体感のある寄せ植えに。
デザインのコツ
白×赤・ピンク・青紫の配色は、春らしい爽やかで明るい印象を演出。そして、背丈のあるユキヤナギを背景に、低めの草花を前面に配置するとバランス良くまとまります。
👉 これにより、まるで「一枚の春の絵画」のような花壇を作ることができます。
和風庭園に清楚なアクセント
ユキヤナギは古くから和風の庭に親しまれており、静けさと上品さを演出する名脇役です。
おすすめの配置
- 飛び石の脇や苔のそばに植えて、枝の流れるような曲線を活かす。
- 黒石や竹垣、石灯籠と合わせると、落ち着いた雰囲気が一層引き立ちます。
デザインのコツ
枝垂れ状の姿をそのまま活かし、剪定で“きれいに整えすぎない”のが和風庭園ではポイント。自然な枝ぶりが、庭全体に四季の情緒を添えてくれます。
👉 静謐な和の空間に「春の清らかさ」を差し込む存在感を発揮します。
生垣・ボーダーとして
ユキヤナギは高さ1〜2mほどで扱いやすく、庭の境界線や花壇の縁取りにぴったりです。
生垣利用の魅力
- 春には白花が一斉に咲き、庭や道路沿いに「雪の帯」ができるような華やかな景観に。
管理のポイント
- 花後に軽く形を整える剪定をすることで、美しいラインをキープできます。
実用性と景観の両立
- 境界の目隠し効果がありながら、枝が細く風を通すので圧迫感を感じにくいのも魅力。
- 防犯・プライバシー確保にも役立ちます。
👉 ボーダーガーデンの一部に取り入れれば、洋風の庭にも自然に溶け込みます。
このように、ユキヤナギは「寄せ植えで春の彩り」「和風庭園で静かなアクセント」「生垣で実用+美観」と、庭づくりに幅広く活用できる万能花木。
そして、配置の工夫次第で、庭全体の雰囲気をグッと高めることができます。
ユキヤナギのよくある質問(FAQ)
ユキヤナギを育て始めると、ちょっとした疑問が出てくるものです。ここでは、初心者の方が特によく抱く質問をまとめ、詳しく解説しました。
そして、「なぜそうするのか?」という理由まで理解することで、育て方のコツがぐっとつかみやすくなりますよ。
Q. 植え付けはいつがベスト?
A. 秋(10〜11月)が最もおすすめ
- 秋は気温と湿度が安定しており、植え付け後に根がしっかり張りやすい季節です。
- 冬の間に根を整え、翌春の花付きにも好影響があります。
- 一方、寒冷地や霜が心配な地域では、春(2〜3月)がベター。
- 芽吹き直前に植えることで、春から一気に根が伸びて定着しやすくなります。
👉 迷ったら「温暖地=秋」「寒冷地=春」と覚えておくと失敗しません。
Q. 剪定はいつ・どこを切ればいい?
A. 花後すぐ(4〜6月)が基本
- ユキヤナギは春の新梢に翌年の花芽を作るため、花後すぐに剪定しないと花芽を切り落とすことになります。
- 外に飛び出した枝は節の上で軽く切り戻すと樹形がまとまりやすくなります。
- 古枝(3〜4年経過した枝)は花付きが悪いため、根元から切って更新し、株を若返らせましょう。
- 冬(12〜2月)はあくまで整理剪定。枯枝・絡み枝・病枝の除去程度に留めるのがコツです。
👉 「花を増やしたい=花後剪定」「整理だけ=冬剪定」と覚えておくと安心です。
Q. 水やりと肥料の基本は?
A. 基本は“控えめ”で十分
水やり
- 地植えは、根付いてしまえばほぼ“雨任せ”でOK。
- 真夏に雨が降らず乾燥が続くときだけ朝夕に補助します。
- 鉢植えは乾きやすいので、表土が乾いたら鉢底から水が流れるまでしっかり与えるのが鉄則。
肥料
- 寒肥(1〜2月):株を充実させるために緩効性肥料を少量。
- お礼肥(5月):花後に疲れた株を回復させるため、控えめに追肥。
- 鉢植えは春〜秋に月1回程度、液肥や緩効性肥料をプラス。
👉 与えすぎると枝ばかり伸びて花が減ったり病気を招くので、「少なめで十分」と意識するのがポイントです。
Q. 挿し木の成功率を上げるには?
A. 清潔な用土・明るい日陰・高湿度が“三種の神器”
- 切り取る枝は、今年伸びた10〜15cmの若枝を選ぶと発根しやすいです。
- 切り口は水に数分浸けて“水揚げ”を行い、発根促進剤(ルートンなど)を薄く塗布すると成功率がさらにアップ。
- 挿し床は赤玉小粒やバーミキュライトなどの清潔な無菌性用土を使用。
- 挿した後は乾燥させないように、透明なカバーやペットボトルを被せて高湿度を維持しましょう。
👉 発根したらすぐに鉢上げせず、しばらく安定させてから植え替えると、株がしっかり育ちます。
このように、ユキヤナギの栽培は「植え付けは季節を選ぶ」「剪定は花後が鉄則」「水やり・肥料は控えめ」「挿し木は環境づくり」がポイント。
そのため、ちょっとした工夫で、毎年雪のような花景色を楽しめるようになります。
まとめ:ユキヤナギで“春の白い景色”を楽しもう
いかがでしたか?
ユキヤナギはとても丈夫で、初心者でも安心して育てられる花木です。そのため、植え付けの時期を選び、排水の良い土を使い、花後に剪定する…
この3つのポイントさえ押さえれば、毎年たっぷりと花を咲かせてくれます。
庭づくりのシーンでも大活躍。
- 春の花壇では、チューリップやムスカリと合わせて寄せ植えに。
- 和風庭園では、飛び石や苔のそばに植えて上品なアクセントに。
- 生垣として並べれば、春には白い花の帯ができて華やかな景観に。
そして、ユキヤナギはまるで庭に春の白いリボンをかけるような存在。ぜひ、あなたの庭にも取り入れて、春ならではの清らかな景色を楽しんでみてください。
関連記事:
- 【ガーデニング初心者必見!】ガーデニングを始める前に知っておきたい基本のキホン
- 【水やりも自動化!!】自動水やり器で時間を有効活用!
- シンボルツリーにおすすめの樹木6選!
- ガーデニングの魅力と効果とは?初心者向け始め方ガイド
- 【洋風の庭に最適!】常緑樹中木の選び方とおすすめ樹種
- 【剪定はゲームで覚える時代へ】玉崎弘志の剪定教室で楽しくマスター!
- 【春ガーデニング初心者必見!】簡単でおしゃれな庭デザインのコツと計画術
- 【おしゃれな庭木・低木で庭を演出!】おすすめ樹種と植え方のコツ
- 【庭の害虫駆除法6選!】自然派~業者対応まで徹底比較
- 四季を香りで彩る!四大香木の庭づくりガイド
- 【ユキヤナギは庭に植えても大丈夫?】実は“注意点あり”
- 【初心者向けガーデニングガイド!】庭作りの基本とおすすめ植物






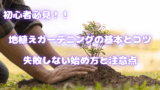

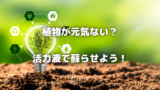





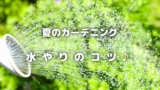


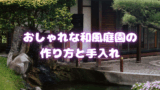
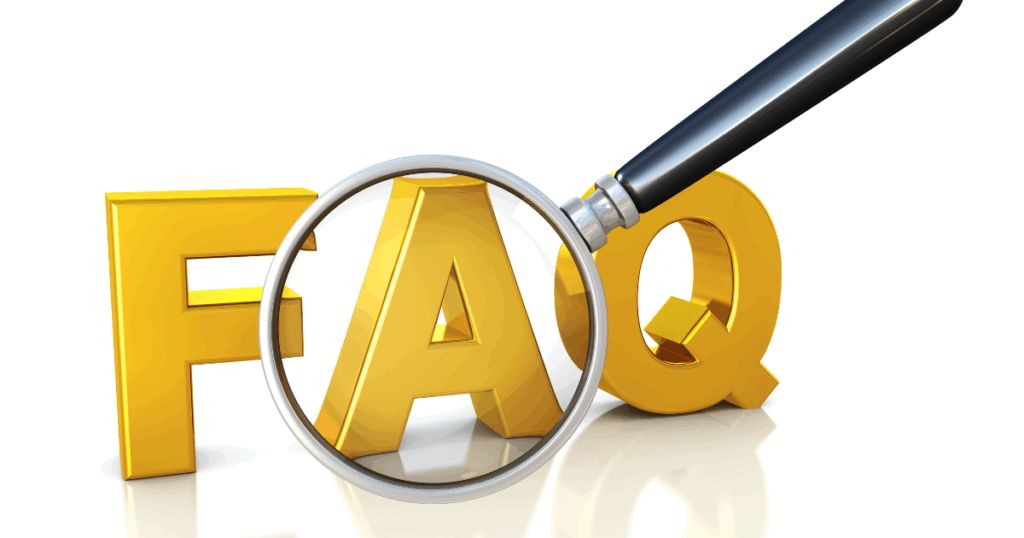

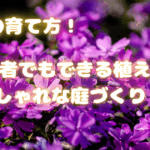
コメント