美しく整った芝生は、庭の第一印象を大きく左右します。
しかし、「芝生が黄色くなった」「部分的に枯れてしまった」といった悩みは、多くの方が経験する共通の問題です。
この記事では、芝生が元気を失う原因を解説し、それぞれに応じた具体的な対策方法をご紹介していきます。

庭全体の美しさを取り戻すヒントにぜひご活用ください。
芝生の元気がなくなる主な原因とは?
美しい芝生を保つには、日々の手入れが欠かせません。しかし、気がつくと「元気がない」「色が悪い」「枯れている」などのトラブルが発生していることも…。
ここでは、芝生の元気を奪う主な5つの原因について、詳しく解説していきます。
1. 水不足や水のやりすぎ:水加減が美しさのカギ
芝生の健康維持には、適切な水分管理が不可欠です。しかし、「乾燥気味だからたくさん水を与えよう」と思って過剰に与えるのもNG。
水不足の場合
- 芝が乾燥し、葉先から茶色く枯れていきます。
- とくに、真夏の炎天下では、数日間でダメージが進行してしまうことも。
水のやりすぎの場合
- 根が常に湿った状態になると酸素不足に陥り、「根腐れ」や「病気(黒斑病など)」の原因になります。
ポイント
夏は早朝または日没後に、土壌がしっかり湿る程度の水やりが効果的です。しかし、表面だけ濡らしても意味がないので、1回でしっかりと深く与えるのが理想です。
2. 日光不足による弱り:芝生は“光合成命”の植物
芝生は日光をたっぷり浴びて光合成を行い、元気に成長します。
しかし、建物の影や高木の下など、日照時間が短いエリアでは、葉が薄くなり、黄色や白っぽく変色することがあります。
- 見た目が悪くなるだけでなく、光合成ができないことで根も弱りやすくなります。
- 芝の種類によっても耐陰性に差があるため、日照条件に合った芝を選ぶことも重要です。
改善策
不要な枝の剪定、建物の影になる部分には耐陰性のある芝(例:シャデーグラスなど)を選びましょう。
3. 栄養不足・肥料切れ:成長が止まる“サイン”を見逃さないで
芝生は「窒素(N)・リン(P)・カリウム(K)」という3大栄養素をバランスよく必要とします。
- 窒素不足・・・葉の色が薄くなり、黄緑〜黄色へ
- リン不足・・・根の成長が鈍る
- カリウム不足・・・病害虫への抵抗力が低下
定期的に芝生専用の肥料を与えないと、芝が弱って病気や雑草に負けやすくなります。
ポイント
春〜秋にかけて年に2〜3回の施肥が目安。芝の様子を見て、必要な成分を補いましょう。
おすすめ肥料
- 有機質配合タイプ(ゆっくり効く)
- 速効性タイプ(急激に回復させたいとき)
4. 病害虫の発生:見逃すと“芝全体が壊滅”することも
芝生にもさまざまな病気や害虫のリスクがあります。そのため、見た目に異変を感じたら、早期対応が肝心です。
害虫の例
- カメムシ・コガネムシの幼虫が根を食害し、突然枯れ始めることも。
- スコップで地面を少し掘ると、白い幼虫が出てくることがあります。
病気の例
- 黒斑病やさび病は、梅雨や秋など湿気の多い時期に発生しやすいです。
- 芝の一部が黒く変色したり、赤茶色の粉のようなものがつくのがサインです。
対策
- 害虫には殺虫剤や幼虫駆除剤
- 病気には殺菌剤の散布や通気性の改善(エアレーション)
5. 土壌環境の悪化:見えない“足元”が原因かも?
芝生の元気がなくなる最大の落とし穴は、土壌の状態です。
水はけが悪い場合
- 土が常に湿って根が呼吸できず、病気の温床に。
酸性に偏った土
- 芝が必要とする栄養分を吸収できず、見た目も生育も悪くなります。
長年放置された庭
- 踏み固められて酸素が不足し、硬い地面になっていることが多いです。
改善策
- エアレーション(穴あけ)で通気性・排水性UP
- 苦土石灰や腐葉土でpH調整と土壌改良を行う
- 定期的な土壌チェックもおすすめです
芝生の元気がないと感じたら…
まずは、「水・光・栄養・病害虫・土」の5つの観点から原因を探ってみましょう。そして、一つひとつを見直すことで、芝生の状態は確実に改善されていきます。
- 水は適量・適時に!
- 日照条件をチェック!
- 肥料で栄養補給!
- 病害虫は早期対処!
- 土壌改良も忘れずに!
美しい芝生を取り戻し、心地よい庭づくりを楽しみましょう。
≪送料無料≫プロも愛用の人気植物活力液!全ての植物にオススメ。
植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」。
植物本来の力を最大限に引き出せます。
芝生の元気を取り戻す!5つの具体的な対策
芝生が元気をなくしたとき、大切なのは“何が足りないのか”“どう補えばいいのか”を正しく見極めて対処することです。
ここでは、初心者でもすぐに実践できる5つの具体的なケア方法をご紹介していきます。
1. 正しい水やりの習慣を身につける
芝生の水やりは「量よりタイミング」がカギです。そのため、間違った水やりは、乾燥や根腐れを招き、芝のダメージにつながります。
理想的なタイミング
- 気温が落ち着く早朝または夕方にたっぷりと与えるのがベスト。
- 日中は水が蒸発しやすく、芝も焼けやすいため避けましょう。
頻度の目安
- 週2〜3回が基本。
- ただし、雨が降った週や気温の低い日は控えめに、猛暑日が続くようなら回数を増やすなど、天候に応じた調整が重要です。
水はけの悪い場所への対策
- いつまでも水たまりが残るような箇所には、排水管の設置や地面に川砂を混ぜるなどの改善が効果的です。
2. 日当たりを確保するための工夫
芝生は光合成を行う植物。そのため、十分な日照がなければ、どんなに水やりや肥料を頑張っても元気を取り戻せません。
影を作るものを整理
- 庭木や生け垣、隣家からの影が原因であれば、高木の剪定や低木の整理で日当たりの確保を。
日陰が避けられない場合
- 日照時間が少ない場所には、耐陰性のある芝を使うのが効果的。
- 例:シャドーグラス(シェードタイプの高麗芝)などは、半日陰でもしっかり育ちます。
3. 肥料の与え方で芝の力を引き出す
芝生の栄養管理は、季節と目的に合わせて変えるのがポイントです。
春・秋(成長期)
- 葉の緑を取り戻し、全体のボリュームを出したいなら、窒素多めの肥料(N)が最適。
- 緩効性の有機肥料もおすすめです。
夏(高温期)
- 肥料焼けを防ぐため、施肥は控えめに。
- どうしても与える場合は、水やりとセットで。
晩秋(冬越し前)
- 根の強化と寒さへの備えには、リン酸(P)中心の肥料を与えると効果的です。
- これにより、春の芽吹きもスムーズになります。
おすすめ肥料
- 芝生専用の粒状タイプや、液体肥料をジョウロに混ぜて使えるタイプが便利です。
4. 病害虫への早期対処と予防策
放置すると芝全体にダメージが広がる病気や害虫。そのため、早期発見・早期対応が元気な芝を保つカギです。
症状が出たらすぐ対処
- 茶色や黒っぽい変色、葉の白い粉(さび病・うどんこ病)、地面に白い幼虫がいるなどの症状が出たら、すぐに殺菌剤・殺虫剤を使用しましょう。
枯れた部分の処理
- すでに傷んでしまった部分は清潔なハサミで切除し、健康な芝への感染拡大を防ぎます。
通気性を改善する
- エアレーション(芝に穴を開けて空気を通す作業)を行うことで、病気を未然に防ぐ効果もあります。
- とくに、湿気が多い時期に有効です。
5. 土壌改良で根本から環境を整える
芝生がうまく育たないときは、見た目ではわからない「土の状態」に原因がある場合も…
水はけの改善
- 粘土質の土には、川砂やパーライトを混ぜて、排水性をアップさせましょう。
酸性土壌のpH調整
- 日本の土は酸性に偏りやすいため、苦土石灰や石灰資材で定期的にpHを調整することが必要です。
年1~2回の土壌診断
- 専用キットを使えば自宅でもpHや肥料成分の過不足が確認できます。
- 必要に応じて土壌改良材や有機肥料で土をリフレッシュさせましょう。
芝生の再生には“段階的な改善”がカギ
元気を取り戻すためには、「水・光・栄養・病害虫・土壌」という5つのポイントをバランスよく整えることが大切です。
そして、小さな変化でも見逃さずに、丁寧にケアを続ければ、数週間〜数ヶ月で元の美しい芝生がよみがえります。
芝生を美しく保つためのメンテナンス習慣
せっかく育てた芝生も、放置してしまうとあっという間に荒れてしまいます。
そこで大切なのが「定期的なメンテナンス習慣」。そして、ほんの少しの手間をかけるだけで、見違えるほどきれいな芝生を維持できます。
1. 月1回の芝刈りで密度を高める
芝刈りは単に見た目を整えるだけでなく、「密度を高めて強く美しい芝生を作る」ために非常に重要です。
定期的に刈ることで…
- 芝が横に広がろうとし、葉の密度が自然に増していきます。
- これにより、雑草の侵入も防げるようになります。
おすすめのタイミング
- 春〜秋の成長期は月1回を目安に。夏は2〜3週間に1回でもOK。
- ただし、1度に刈る量は草丈の1/3以内に抑えましょう。深く刈りすぎると芝が弱る原因になります。
👉 芝刈り機の使用で作業もラクに。そして、狭い場所や細かな部分は芝用バリカンが便利です。
2. 雑草取りで栄養の“横取り”を防ぐ
芝生と雑草は地中の栄養や水を奪い合う関係にあります。そのため、放置すると、芝生が本来吸収すべき養分が雑草に取られ、元気がなくなってしまうことも…。
こまめに取り除く習慣を
- 雑草は成長が早く、根も深いため、見つけたらすぐ抜くことが大切です。
おすすめ道具
- 根から抜ける雑草抜き専用フォークや除草ハサミを使うと、効率よく作業できます。
雑草が多い場合の対策
- 防草シートや芝生専用の除草剤(選択性除草剤)を使うのもひとつの方法です。
3. エアレーション(穴あけ)で根に酸素と栄養を届ける
芝生の下の土は、人が歩いたり雨が降ったりすることで徐々に固く締まっていきます。すると、根に十分な酸素が届かず、成長が鈍り、見た目もスカスカに。
そのため、そこで行いたいのが「エアレーション」という作業です。
エアレーションとは?
- 芝生に小さな穴を開けて通気性・排水性を高める作業。
- 根に酸素や水、肥料が行き届くようになります。
年に1〜2回が目安
- 春か秋(成長期)に実施すると効果的。
- スパイク付きのローラーや専用のエアレーター器具で手軽に行えます。
効果
- 根の活性化/水はけ改善/病気の予防にもつながるので、芝の“若返り”にも効果絶大です。
少しの手間で“プロのような芝生”に
芝生を美しく保つ秘訣は、ちょっとしたメンテナンスを習慣化することです。
そのため…
- 月1回の芝刈りで密度アップ
- 雑草取りで栄養の浪費を防止
- エアレーションで根をリフレッシュ
この3つを意識するだけで、あなたの芝生は驚くほど美しく、力強く育っていきます。
まとめ:原因を見極めて芝生の健康を回復しよう
いかがでしたか?
芝生の元気がなくなる原因には、水・光・栄養・病害虫・土壌など複数の要素が関係しています。そのため、まずは原因をしっかり特定し、それに合わせた対策を段階的に実施することが大切です。
- 適切な水やりと日照管理
- 定期的な肥料と病害虫チェック
- 土壌改良とメンテナンスの習慣化
そして、これらを実践することで、芝生本来の緑を取り戻し、庭全体の美しさも保たれます。
おすすめサービス
関連記事:
- 剪定、伐採なら「お庭マスター」
- 【ガーデニング初心者必見!】誰でも簡単にできる!一年中「緑の芝生」を保つ3つの秘訣!
- 【冬でも青々とした緑の芝生を実現】芝生用着色剤の魅力
- 天然芝と人工芝には「どのようなメリットとデメリット」があるのか?
- 【芝生の手入れ完全ガイド】初心者でも失敗しない5つの基本ステップ
- 【芝生を張る時期はいつ?】失敗しないための完全ガイド!
- 芝生にアリの巣ができた時の対策&予防方法を徹底解説!
- 【芝生をやめたい?】ローメンテナンスで魅力的な庭を作る方法
- 【芝生が枯れた?】水不足でも復活できる再生法と正しい水やり完全ガイド
- 庭におすすめの芝生の種類と選び方
- 和モダンの庭に映える芝生とデザイン術のすべて
- 【秋の芝生手入れ完全ガイド】刈り込み・補植・肥料・雑草対策
- 【剪定や草刈りはプロに任せるのが正解!】庭手入れ業者の選び方と依頼方法
- 【忙しいあなたに!】お庭110番で庭の手入れをもっとラクに
- 【満足の草刈りサービス!】全国対応でお庭の手入れが楽々!
- 芝生のほったらかしで起きる問題とその対策方法
- 【冬の芝生手入れ法】寒さから芝を守るポイント
- 【高麗芝とは?】初心者向けステップバイステップガイド
- 【姫高麗芝とは?】初心者向けステップバイステップガイド
- 【TM9とは?】初心者でも簡単に育てられる省管理型芝生の完全ガイド
- 【西洋芝とは?】初心者向けステップバイステップガイド


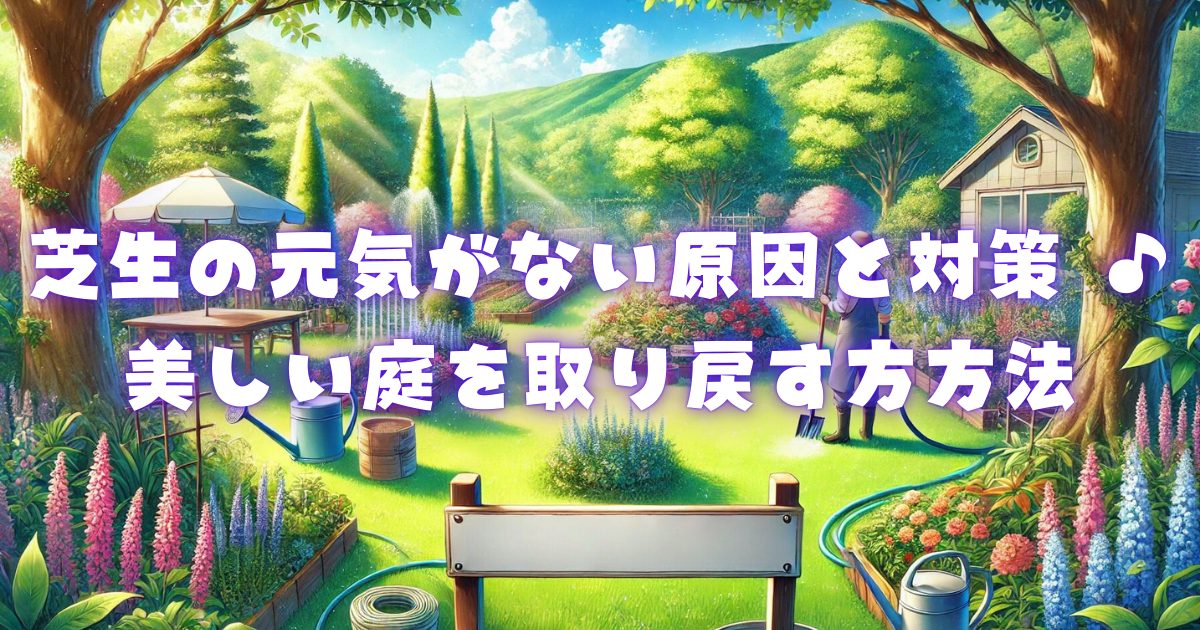




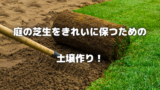






コメント