庭づくりで常緑樹か落葉樹かは大きな分岐点。
なぜなら、常緑樹は目隠し・防風・日除けなど実用面に強く、冬でも緑の景観が保てるからです。しかし、一方で、圧迫感や冬の日照低下などのデメリットも…
この記事では、初心者でも後悔しないように、常緑樹のメリット・デメリットと選び方のコツ、剪定・水やり・肥料の基本、おすすめ樹種&下草までをわかりやすく解説していきます。

木は簡単に植え替えるものではありません。だからこそ、最初の選び方がとっても大切。この機会にしっかりと情報をキャッチして、あなたのお庭に最適な木を選びましょう!
常緑樹とは?落葉樹との違い
庭づくりを考えるとき、まず悩むのが「常緑樹」と「落葉樹」の選択です。しかし、どちらも庭の景観や機能性に大きな影響を与えるため、特徴をしっかり理解しておくことが大切です。
常緑樹の特徴
常緑樹は、その名の通り一年を通して緑の葉を保つ樹木です。また、冬でも葉を落とさないため、庭が常に緑豊かな印象になります。
さらに、以下のようなメリットがあります。
- 目隠しやプライバシー確保・・・
通年葉が茂っているので、隣家や道路からの視線を遮る生け垣やシンボルツリーに最適。 - 防風・防音効果・・・
風を和らげたり、騒音を軽減する役割も担ってくれる。 - 景観の安定感・・・
季節を問わず緑があることで、庭全体が「整っている」印象になる。
ただし、常緑樹は樹冠が濃く影をつくるため、下草や花壇の日当たりを妨げやすい点には注意が必要です。
落葉樹の特徴
一方で落葉樹は、春〜夏は葉を茂らせ、秋には紅葉、冬は落葉して枝姿になる樹木です。そのため、四季ごとの変化を楽しめるのが最大の魅力です。
- 夏は涼しい木陰を提供・・・
葉が茂って日差しを遮り、自然な日よけになる。 - 冬は日差しを取り込める・・・
葉を落とすため、家や庭に太陽光を届けて暖かさを確保できる。 - 季節の彩り・・・
新緑、紅葉、落葉と、自然の変化を感じられるため、景観に動きが出る。
ただし、落ち葉の掃除が必要だったり、冬場は目隠し効果が弱まるといったデメリットもあります。
庭づくりの黄金バランス
庭を快適に保ちつつ景観を美しくするには、常緑樹+落葉樹+下草の組み合わせがおすすめです。
- 常緑樹:基盤となる「背景」や「目隠し」
- 落葉樹:季節感や変化をプラス
- 下草・低木:彩りや空間のつなぎ役
このバランスを意識することで、季節ごとに表情を変えながらも、通年で快適かつ美しい庭をつくることができます。
👉 「緑を切らさず、でも四季を楽しめる」そんな理想の庭づくりを目指すなら、常緑樹と落葉樹の違いを理解し、バランスよく取り入れるのが成功のカギです。
常緑樹のメリット:庭を一年中美しく、暮らしを快適に
庭木選びに迷ったとき、多くの人が候補にするのが「常緑樹」です。
なぜなら、常に緑を保つ美しさはもちろん、目隠しや防風といった実用性、さらには掃除や管理のしやすさまで、多くの利点を持っているからです。
一本あるだけで庭や住まいの印象が大きく変わる常緑樹。では、その魅力を具体的に見ていきましょう。
1) 一年中、緑の景観が続く
常緑樹の一番の魅力は、冬でも緑を絶やさない安定感です。
とくに、落葉樹が葉を落として枝だけになる季節でも、常緑樹が庭を彩ってくれるため、寂しさや荒れた印象を与えません。
- 和風庭園では松やマキが景観を引き締め、落ち着いた雰囲気を演出。
- ナチュラルガーデンではオリーブやシマトネリコが自然な柔らかさをプラス。
- モダン外構にはコニファーやトネリコ類がシンプルで洗練された印象を与えます。
どんな庭のテイストにも溶け込みやすく、全体のバランスを整える“背景”の役割を担ってくれるのです。
2) 目隠し・防風・日除けの“自然シールド”
常緑樹は、ただ美しいだけでなく、暮らしを快適にしてくれる頼もしい存在でもあります。
目隠し
- 常緑樹を列植することで、通りや隣家からの視線を自然に遮り、プライベート空間を守ります。
- 人工フェンスより柔らかく圧迫感が少ないのも魅力。
防風
- 冬の冷たい北風を遮り、家の周りの体感温度を和らげます。
- 植栽の配置によって「風の通り道」を変えられるため、エクステリア設計の一部としても有効です。
日除け
- 夏には葉が直射日光をやわらげ、窓から入る熱をカット。
- エアコンの使用を抑えて省エネにもつながります。
“庭木=景観”だけでなく、生活を守る天然のシールドとしての役割は、常緑樹ならではのメリットです。
3) 掃除・管理の手間が少なめ
落葉樹のように大量の葉を一度に落とすことがないため、掃除やゴミ出しの負担が少ないのも嬉しいポイント。とくに、住宅街では落ち葉が近隣へ飛んでトラブルになることもあるため、常緑樹は安心です。
また、葉が厚い樹種は乾燥しにくく、葉の入れ替わりも少しずつ行われるため、手間がかかりにくい管理性が魅力。
そのため、忙しい人や庭仕事に慣れていない初心者でも扱いやすいです。
4) 雪・乾燥に強い樹種も選べる
常緑樹の中には、環境に強い品種も豊富です。
雪に強いタイプ
- コニファー類(ゴールドクレスト、ブルーヘブンなど)は枝がしなやかで折れにくく、雪国の庭でも安心。
乾燥に強いタイプ
- オリーブやトネリコ類は比較的乾燥に耐えやすく、水やりの手間を抑えられます。
そして、住んでいる地域や庭の環境に合わせて選べるため、失敗しにくい庭木選びができるのも大きなメリットです。
このように、常緑樹は、景観だけでなく「暮らしを守り、手間も減らし、環境にも強い」万能の庭木です。そのため、一本植えるだけでも庭の印象や住まいの快適さを大きく変えることができます。
常緑樹を植えるデメリット(&対策)
常緑樹は一年中緑を楽しめる反面、植える位置や樹種を間違えると「暗い」「管理が難しい」といった不満につながることもあります。
しかし、多くはちょっとした工夫や組み合わせで解決可能です。では、よくある失敗と対策を見ていきましょう。
圧迫感・重たい景観
よくある失敗
- 常緑樹ばかりを並べて植えた結果、庭全体が暗く見えてしまう。
- とくに、住宅街の狭小地では「壁のように見える」ことも…
最低限の対策
- 株立ち樹形(幹が複数に分かれていて軽やか)や、葉が細かく透け感のあるタイプを選ぶと圧迫感を軽減。
- さらに、落葉樹や季節の花を組み合わせて彩りを加えると景観が明るくなる。
下草が育ちにくい
よくある失敗
- 常緑樹の濃い木陰のせいで土がむき出しになり、殺風景な印象に…
- 苔も育ちにくいケースがある。
最低限の対策
- ギボウシ・ヒューケラ・フッキソウなど、耐陰性のある下草を選べば緑が保てる。
- 加えて、枝を透かして光を落とす剪定を行えば、下草が元気に育つ環境をつくれる。
寒さに弱い品種がある
よくある失敗
- オリーブやシマトネリコなどは、暖地向きのため寒冷地では冬に葉が傷んで枯れ込むことがある。
最低限の対策
- 植える前に必ず耐寒性(耐寒ゾーン)を確認。
- 寒冷地では鉢植えにして冬は室内へ移動、または不織布やわらで防寒対策をするのがおすすめ。
冬の日照を遮る
よくある失敗
- 南向きの窓の前に大きな常緑樹を植え、冬の貴重な日差しを完全に遮ってしまう失敗。
- 室内が暗く寒くなり後悔する例が多い。
最低限の対策
- 南面に植える場合は、樹幅や高さを抑えることが鉄則。
- 円錐形で影の小さいコニファーを選ぶのも有効。
- 落葉樹と組み合わせて「夏は日よけ、冬は日差し確保」を意識すると快適。
四季の変化が乏しい
よくある失敗
- 常に緑があることで安心感はあるが、「景色が変わらず単調」と感じることも…
- 庭が“平坦”に見えてしまう。
最低限の対策
- ツバキやサザンカなど花の咲く常緑樹を取り入れると季節感が出る。
- さらに、紅葉が楽しめる低木や草花をミックスすると、常緑樹の安定感と四季の変化を両立できる。
このように、常緑樹は「便利で美しい庭木」ですが、配置・樹種の選び方・組み合わせで印象が大きく変わります。逆に言えば、ちょっとした工夫でデメリットをすべて魅力に変えることができるのです。
“失敗しない”常緑樹の選び方(7つのチェック)
常緑樹は一度植えると簡単には移動できません。
だからこそ、植える前にしっかりと条件をチェックしておくことが「後悔しない庭づくり」のコツです。そのため、以下の7つを押さえておくことで、初心者でも安心して選べます。
1) 目的を明確にする
常緑樹といっても種類ごとに特徴は大きく異なります。
- 目隠し重視・・・シマトネリコや常緑ヤマボウシ
- 防風・防音・・・コニファー類やトネリコ類
- 日除け・シェードツリー・・・クスノキ、シラカシ
- 香りを楽しむ・・・キンモクセイ、ツバキ
- 実を楽しむ・・・オリーブ、レモン、フェイジョア
- 低メンテナンス・・・常緑低木(アベリア、ヒイラギナンテン)
👉 最初に「何を優先するか」を決めておくと、迷わず樹種を選べます。
2) 植栽位置を確認する
植える方角や環境によって、木の育ち方も大きく変わります。
- 南面・・・
日射が強い → 樹高や樹幅に注意(冬の日差しを遮らない配置が重要) - 北面・・・
日照不足 → 耐陰性のある品種(アオキ、シェフレラ)がおすすめ - 動線や駐車場付近・・・
枝が張り出すと邪魔になる → コンパクトな樹形を選ぶ - 窓前・・・
影や落ち葉の影響を考慮し、距離を取る
👉 「どこに植えるか」=「その木が活躍できるかどうか」を決める大切なポイントです。
3) サイズ(最終樹高・樹幅・離隔距離)
苗木のうちは小さくても、10年後には建物より大きくなる品種もあります。
- 樹高・・・最終的にどこまで伸びるか?
- 樹幅・・・枝が広がって通路や隣家に干渉しないか?
- 離隔・・・建物や塀、配管、電線からどのくらい離す必要があるか?
👉 「植えた時はちょうど良かったのに、数年後に邪魔に…」という失敗はこの確認不足から生まれます。
4) 成長スピード
成長が早い木は、目隠しとして早く役立つ反面、剪定コストが増えるのが難点です。
- 成長が早い・・・シマトネリコ、トネリコ類(剪定年2~3回必要)
- 成長が遅め・・・オリーブ、ソヨゴ(管理しやすい)
👉 株立ち樹形は自然に枝が分かれるため、剪定しても樹形が乱れにくく、初心者におすすめです。
5) 土壌・排水環境
常緑樹は「水はけの悪さ」に弱い品種が多いです。
- 乾きやすい土壌・・・
水やりをしっかり行う or 腐葉土を混ぜて保水性UP - 湿りやすい土壌・・・
盛土で高植えする or 砂やパーライトを混ぜて排水性を改善 - pH・・・
弱酸性〜中性が標準。オリーブなど一部は弱アルカリ性でもOK。
👉 植え付け前に土壌改良をしておくと、その後の生育が格段に安定します。
6) 根のタイプ
根の張り方は意外と見落とされがちですが、とても重要です。
- 浅根性(シマトネリコ、カシ類など)・・・
舗装や配管を押し上げるリスク → 建物から十分に離して植える - 深根性(オリーブ、コニファー類など)・・・
しっかり根を下ろすが、植え穴を深めに掘り、土壌改良が必要
👉 将来のトラブルを避けるために、根の特性を把握したうえで植栽場所を選ぶことが必須です。
7) 手入れのしやすさ
常緑樹は基本的に落葉が少ないですが、剪定や花がら掃除が必要なものもあります。
- 剪定・・・頻度は年1回で済むか、年3回必要か?
- 病害虫・・・カイガラムシ・ハダニなどに弱い樹種もある
- 花がら・・・ツバキ・サザンカは大量に落ち、掃除の手間が増える
- 落葉量・・・常緑樹でも新陳代謝で少しずつ落ちるため、通路や屋根の近くは注意
👉 自分の「管理できる範囲」を見極めて選べば、長く快適に楽しめます。
このように、常緑樹選びは「好み」だけでなく、目的・環境・管理コストまで考えるのが成功の秘訣です。そして、7つのチェックをクリアすれば、失敗知らずで理想の庭木に出会えます。
庭木として人気の常緑樹おすすめ8
常緑樹といっても種類はさまざま。そのため、庭の目的や雰囲気に合わせて選ぶことで、景観も機能性もぐっと高まります。
ここでは、「目隠し・管理ラク系」と「明るい樹形・シンボル系」に分けておすすめの8種をご紹介していきます。
目隠し・管理ラク系(常緑広葉樹)
ソヨゴ
成長がゆっくりで管理がしやすく、女性や初心者にも扱いやすい庭木。とくに、秋に赤い実がつく姿が美しく、冬の庭を彩ります。
また、耐陰性があるので北側の庭や半日陰でも育ちやすく、落ち葉も少ないため掃除の手間も軽減。ただし、雌雄異株なので、実を楽しみたい場合は雌株+雄株をセットで植えるのがおすすめです。
モチノキ
丈夫で環境を選ばず育ちやすい、頼れる常緑樹。とくに、光沢のある濃緑の葉が上品で、和風・洋風どちらの庭にも馴染みます。
そして、剪定に強く、樹形を整えやすいので生垣や目隠し樹としても大活躍。また、耐病性もあり、都市部や海風が当たる地域でも元気に育ちます。
ヒメシャリンバイ
春に白い花を咲かせ、秋には黒紫の実をつけ、常緑の葉は季節によって色合いが変化。とくに、花・実・葉の三拍子が揃った多彩な魅力を持つ庭木です。
さらに、耐潮性があり沿岸部や風の強い地域でも比較的強く育つのが特徴。そして、低木としてグランドカバー的にも使えます。
キンモクセイ
秋に甘く濃厚な香りを放つ、日本人にとって馴染み深い常緑樹。そのため、庭に1本あるだけで「秋の香りスポット」に早変わりします。
そして、枝葉はよく茂り、目隠しや防風にも効果的。ただし、強剪定をすると翌年の花付きが悪くなるため、剪定は花後に軽めに行うのがコツです。
明るい樹形・人気シンボル系
シマトネリコ
軽やかに透ける葉が爽やかで、現代住宅のシンボルツリーとして圧倒的人気。
そして、株立ちの樹形が美しく、和洋どちらの家にも合います。しかし、成長が早いため、定期的な剪定は必要ですが、その分早く目隠し効果を得られるのがメリット。
また、寒冷地では冬に葉が傷みやすいので、防寒対策をすると安心です。
オリーブ
シルバーグリーンの葉が特徴で、地中海風やドライガーデンに映えるシンボルツリー。しかし、乾燥には強い一方、排水性の悪い土壌では根腐れを起こすため、植え付け場所の土改良が必須。
そして、耐寒性はやや弱めなので、寒冷地では鉢植えにして冬は室内管理が安心です。また、果実を収穫できる楽しみもあります。
マホニア・コンフューサ
細くシャープな葉を持ち、モダンな外構や洋風の庭によく合います。とくに、耐陰性が高く、半日陰や北側の庭でも元気に育つため「暗くなりがちな場所の救世主」。
また、枝があまり立ち上がらず、低めの樹形でまとまりやすいので、管理も比較的ラク。そのため、独特の雰囲気を演出したい方におすすめです。
コニファー(円錐形)
ゴールドクレストやブルーヘブンなど、円錐形のコニファーは庭のシンボルとして人気。また、すっきりと縦に伸びるため、影がコンパクトで冬の日照を確保しやすいのも魅力です。
とくに、洋風・北欧風の外構に相性抜群で、クリスマスシーズンにはイルミネーションとの組み合わせも楽しめます。
このように、常緑樹は「目隠し・管理性」を優先するか、「シンボル性・デザイン性」を重視するかで選び方が変わります。
そして、どの品種も特徴がはっきりしているので、庭の目的+ライフスタイルに合わせて選ぶことが、失敗しないポイントです。
常緑樹の“下草”に合う植物(半日陰~日陰向き)
常緑樹の足元は、どうしても濃い木陰になりがちで「土がむき出し」「雑草だらけ」となってしまうことがあります。そこでおすすめなのが、耐陰性が高く、見た目も楽しめる“下草”です。
また、木漏れ日や日陰でも元気に育ち、庭全体に奥行きと彩りを与えてくれます。
ギボウシ(ホスタ)
耐陰性が非常に高く、半日陰〜日陰の庭の定番。
とくに、大きな葉が重なり合って茂るため、常緑樹の足元をしっかりと引き締めてくれます。また、品種によって葉色は黄緑〜青みがかった緑まで多彩で、花も涼しげな薄紫色。
そして、「和風にも洋風にも合う万能下草」として人気です。
ヒューケラ
カラーリーフの代表格。そのため、赤、銅、ライムグリーン、チョコレートブラウンなど、バリエーション豊かな葉色が楽しめます。
また、常緑に近い性質を持ち、冬でも庭を明るく演出。そして、花も小さなベル型で可愛らしく、「足元にアクセントを添えたいときの主役」になります。
アジュガ
地を這うように広がるグラウンドカバー。そして、春には青紫の花穂を立ち上げ、落ち着いた木陰を一気に華やかに変えてくれます。
また、密に育つため雑草抑制効果が高く、管理の手間も軽減。そのため、「実用性と彩りを兼ね備えた一石二鳥の下草」です。
フッキソウ
常緑の低木で、木漏れ日程度の環境でも安定して育つのが魅力。とくに、日本の庭園でも古くから使われてきた定番の下草で、和風の庭と相性抜群。
また、株がまとまって広がるため、整った足元を演出できます。
クリスマスローズ
冬〜早春にかけて花を咲かせる貴重な存在。とくに、木立の下でも元気に育ち、シェードガーデンを華やかにしてくれます。
また、花色のバリエーションも多く、「冬の寂しい庭に彩りを添える救世主」です。
シダ類
半日陰〜日陰を好み、ナチュラルで涼しげな雰囲気を演出。また、常緑性のシダも多く、一年中グリーンを保てます。
とくに、雑木風の庭や自然派ガーデンにおすすめです。
足元づくりのコツ
常緑樹の足元を美しく保つには、植える植物の選び方だけでなく「環境づくり」も重要です。
- 枝透かし剪定で木漏れ日と風通しを確保 → 下草の蒸れを防ぎ、病害虫の予防にもなる
- マルチングで乾燥防止&雑草抑制 → バークチップや腐葉土を敷けば見た目もナチュラル
- 3層構成(常緑+カラーリーフ+多年草)で立体感を出す → 一年中スカスカにならず、季節ごとに変化が楽しめる
👉 例えば、ソヨゴの足元に「ヒューケラ+ギボウシ+アジュガ」を組み合わせることで、春は花、夏は葉のボリューム、冬は常緑で、一年を通じて足元が映える庭になります。
このように、常緑樹を植えるだけでは庭は完成しません。
そのため、足元に“下草”を添えることで、緑が立体的になり、四季を通じて美しく保つことができます。まさに「庭の完成度を一段引き上げる仕上げのひと手間」といえるでしょう。
お手入れの基本(剪定・水やり・肥料)
庭木を長く健康に育てるためには、日々のお手入れが欠かせません。
ただし、「難しそう…」「回数が多くて大変そう」と思われがちですが、実はちょっとした“コツ”を押さえるだけで管理がぐっとラクになるのです。
ここでは、常緑樹を中心にした基本の3大ケアをご紹介していきます。
剪定:回数より「質」と「時期」
常緑樹の剪定は、形を整えるよりも「風通しを確保する」ことが目的。
常緑樹(シマトネリコ、ソヨゴなど)
- 3〜6月に軽い剪定がベスト。
- 混み合った枝を間引き、外周を軽く整える程度でOK。
- 強剪定は木にダメージを与えるので避けましょう。
花木(キンモクセイ、ツバキなど)
- 花が咲き終わった直後に軽く枝を整理すると、翌年の花芽をしっかり残せます。
- 剪定時期を誤ると花が咲かなくなるので要注意です。
高木・太枝・電線付近
- 安全性が最優先。
- 無理をせず、プロの庭師に依頼するのが安心です。
水やり:定植直後は“根鉢まで届く量”
庭木の水やりは「ちょっと湿らす」では不十分。根鉢までしっかり水を届けることが大切です。
植え付け直後〜1〜2か月
- 活着(根が広がる)までは、毎日〜隔日でたっぷり。
- 目安は「鉢底から水が抜けるくらい」まで与えること。
活着後
- 基本は降雨に任せ、猛暑期や乾燥が続くときだけ、朝に様子を見て補水。
- 夜間の水やりは蒸れや病気の原因になるので避けましょう。
自動化の工夫
- タイマー付きの自動水やり機を導入すれば、旅行中や忙しい日でも安心。
- 節水にもつながります。
肥料:春と秋の“少量・分施”が基本
肥料は「多ければ良い」わけではなく、少量を必要なタイミングで分けて与えることがコツです。
春(3〜4月)
- 生長期が始まる直前に緩効性肥料を少しずつ与えると、枝葉の伸びが安定します。
秋(9〜10月)
- 根を太らせて冬越しの準備をする大切な時期。
- ここで栄養を補給しておくと、翌年の芽吹きがぐっと良くなります。
- ただし与えすぎると冬に病害虫が出やすくなるので注意。
真夏
- 暑さで弱っている時期に肥料を与えると逆効果。
- 病害虫を誘発するので、控えるのが正解です。
このように、常緑樹のお手入れは「回数をこなす」よりも「適切なタイミングと方法」を押さえるのがポイント。とくに、剪定・水やり・肥料の3つをバランスよく行うことで、庭木は驚くほど元気に育ち、四季を通じて美しい姿を楽しめます。
よくある失敗Q&A(即解決)
常緑樹は便利で美しい庭木ですが、選び方や植え方を間違えると「思っていたのと違う…」という結果になることもあります。
ここでは、初心者がよくつまずくポイントをQ&A形式で解説し、すぐに実践できる対策をご紹介していきます。
Q. 南面に目隠しで常緑を並べても大丈夫?
A. 冬の日照低下に要注意。
南側は冬の貴重な日差しが入る場所。そのため、常緑樹をびっしり並べてしまうと、室内や庭に光が届かず寒々しくなります。
解決法
- 樹幅を抑えやすい円錐形のコニファーや株立ち樹形を選ぶ
- 建物や窓との間に十分な離隔(距離)を取る
- 常緑樹を点在させ、間に落葉樹を混ぜることで「夏は日よけ・冬は採光」の両立が可能
Q. 下草が全然育たない…
A. 常緑樹の濃い木陰が原因です。
葉が茂りすぎて光が届かないと、どんな下草も弱りやすくなります。
解決法
- ギボウシやヒューケラなど、耐陰性の強い下草を選ぶ
- 定期的に枝透かし剪定を行い、木漏れ日を確保
- 土の表面をマルチング(バークチップ・腐葉土など)して乾燥と雑草を防止
- 水やりは表面だけ濡らすのではなく、根まで届く量を与えることが大切
Q. 寒冷地でも育つ常緑は?
A. 耐寒性のある樹種を選べば大丈夫です。
常緑樹は暖地向きが多いですが、寒冷地にも適した種類があります。
解決法
- コニファー類(ブルーヘブン、エメラルドグリーンなど)
- ツバキ・サザンカ(防寒対策をすれば開花も楽しめる)
- マサキ(刈り込みに強く、生垣にも向く)
- 植えるときは耐寒域(ハーディネスゾーン)を確認する
- 強風にさらされないよう、建物の陰や塀の内側に植えると冬のダメージを軽減できる
Q. 剪定は自分でやってOK?
A. 基本の軽剪定なら初心者でも可能です。
常緑樹は年1〜2回、混み合った枝を間引いたり形を整える程度の剪定で十分。
解決法
- 高枝切りバサミや小型ノコギリを使って自分で軽剪定
- 花木は花が咲き終わった直後に整えると翌年も花付きが良い
- 高所・太枝・電線付近は安全のため無理せずプロに依頼。
- 怪我や事故を防ぐためにも「できる範囲」と「任せる範囲」を分けるのが鉄則
このように、常緑樹の失敗は「配置」「管理」「品種選び」でほぼ防ぐことができます。また、ちょっとした工夫でデメリットを解消できるので、怖がらずにチャレンジしてみましょう。
チェックリスト:植える前に“ここだけは”
庭木は一度植えると簡単に動かせません。だからこそ、植える前に最低限の確認をしておくことが「失敗しない庭づくり」の第一歩です。
そのため、以下のチェックを済ませてから植えると、後悔のリスクをぐっと減らせます。
目的(目隠し/防風/日除け/香り/低メンテ)が明確
「何となく緑が欲しいから」で植えると失敗の元。
- プライバシー重視なら → 密に葉が茂るソヨゴ・モチノキ
- 日除け重視なら → 樹冠が広がるシラカシやクスノキ
- 香りを楽しみたいなら → キンモクセイやツバキ
👉 “目的に合う木=満足度が高い木” です。
最終サイズ(樹高・樹幅)と離隔を把握
苗木は小さくても、10年後には家より大きくなる場合もあります。
- 樹高・・・電線に届かないか?
- 樹幅・・・駐車スペースや隣地に枝がかからないか?
- 離隔・・・建物・塀・配管から十分距離をとっているか?
👉 植えた後に「大きくなりすぎた!」と後悔する人が非常に多いので、必ず事前に確認を。
方角・日射・風・窓・駐車・動線を確認
植える位置によって木の役割やトラブルが大きく変わります。
- 南面・・・冬の日差しを遮らないよう注意
- 北面・・・耐陰性のある品種を選ぶ
- 窓前・・・視線を遮りつつ、光と風を確保する配置に
- 駐車・通路・・・枝張りで動線を邪魔しないように計画
👉 「庭木=景観」だけでなく「生活動線との調和」も忘れずに。
土壌の排水・pHをチェック(必要なら改良)
土壌は木の健康を左右する基盤です。
- 水がたまりやすい → 盛土・砂混合で排水性UP
- 乾燥しやすい → 腐葉土や堆肥を混ぜて保水性UP
- pH(弱酸〜中性が標準)をチェック
👉 土壌改良をしてから植えれば、その後の成長が格段に安定します。
根のタイプと配管・舗装への影響を確認
根は見えない分、後から問題になりやすい部分です。
- 浅根性(シマトネリコ、カシ類) → 舗装を持ち上げる恐れ
- 深根性(オリーブ、コニファー) → 植え穴を深めに掘り、しっかり改良
👉 配管や塀の近くには浅根性の木を植えないのが鉄則です。
剪定・清掃の手間は許容範囲
庭木は放置できません。
- 剪定は年1回で足りるか?
- 花がらや落ち葉はどれくらい出るか?
- 病害虫に弱くないか?
👉 「管理できるかどうか」を想像してから選ぶと、後々のストレスを防げます。
下草計画(耐陰性+カラーリーフ)まで設計済み
常緑樹の足元は木陰になりがち。そのため、放置すると土がむき出しになり、雑草だらけになります。
- ギボウシ・ヒューケラなど耐陰性下草で彩りをプラス
- アジュガでグラウンドカバー&雑草抑制
- 常緑+カラーリーフ+多年草を組み合わせて一年中スカスカ感を防止
👉 足元まで計画してこそ「完成度の高い庭」になります。
このように、常緑樹はただ植えるだけでなく、目的・環境・手間・足元の演出までをトータルで考えるのがポイント。とくに、このチェックリストをクリアすれば、失敗知らずで理想の庭木選びができます。
まとめ:常緑樹は“計画性”でメリットが活きる
いかがでしたか?
常緑樹は、一年中緑を保ちながら、目隠しや防風、日除けとしても頼れる庭木です。ただし、圧迫感や下草が育たない、冬の日照不足や寒さでのダメージといった問題が起きることもあります。
でも安心してください。
植える前に「目的」「環境」「最終サイズ」をきちんと確認し、株立ちの樹形を選んだり、下草を組み合わせたり、枝透かしで光と風を取り込む工夫をすることで、デメリットはほとんど解消できます。
👉 この基本さえ押さえれば、初心者でも失敗なく常緑樹を楽しめます。庭の“主役の緑”を計画的に選んで、長く心地よい空間を育てていきましょう。
関連記事:
- 【初心者向け】シンボルツリーを選ぶ時の注意点
- 【ガーデニング初心者向け】落葉樹を植えるメリットとデメリット
- 【ガーデニング初心者向け】地植えとは?地植えをする前に知っておくべきポイント!
- 【落葉樹の魅力】四季を通じて家族と楽しむ自然の恵み
- 【常緑樹中木】で洋風な庭をつくろう!
- 【庭木の剪定は自分でできる!】 初心者でも失敗しないコツ
- 【初心者向け】おしゃれな庭に欠かせない!庭木の選び方と配置のコツ
- 【剪定業者の魅力♪】剪定業者に依頼すべき5つの理由
- 【庭が劇的に変わる!】評判の庭木手入れ業者を今すぐチェック
- 【庭木の剪定を学習】庭の美を引き出す剪定術
- 【庭にソテツを植えてみよう!】庭を彩る魅力的な植物とは?
- 【南国気分を味わう!】日本の気候でも育つ庭木5選
- ココスヤシでおしゃれな庭を演出する方法
- 【金木犀で庭をおしゃれに彩る方法!】初心者でも簡単にできる庭作り
- 【庭に蝋梅を植える方法と育て方】美しい冬の花を楽しむ庭作り
- 【沈丁花を庭に植える方法】香り豊かな庭を作るポイント
- 【庭にクチナシを植える方法とコツ】初心者向けガイド
- 【四大香木】庭で楽しむ四季の香り
- 【ユキヤナギの育て方】初心者でも簡単に育てられる美しい花木












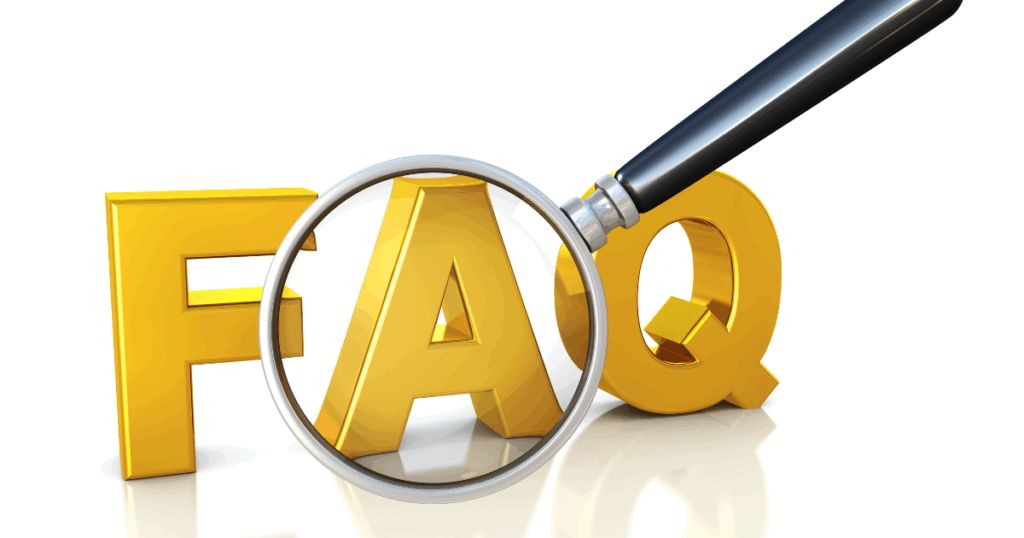



コメント