「剪定っていつやればいいの?」「どこを切ればいいのかわからない…」そんな悩みはありませんか。剪定は見た目を整えるだけでなく、木の健康のためにも欠かせない作業です。
この記事では、剪定の最適な時期・基本の道具・正しい手順・安全対策まで、初心者にもわかりやすく解説していきます。

庭木はどんどん成長していくので、定期的に剪定を行わなければいけません。
ぜひ参考にしてください。
剪定に必要な基本道具と失敗しない選び方
剪定は「どの道具を使うか」で、疲れやすさ・仕上がり・安全性が大きく変わります。
しかし、切れないハサミや、用途に合わないノコギリを使うと、枝がつぶれて木が弱ったり、作業に余計な時間がかかったりする原因に…
そのため、最初に正しい道具を揃えるだけで…
- 作業はラクに
- 木へのダメージは最小限に
- 剪定後もきれい
が一気に叶います。
剪定バサミ:最も出番の多い基本アイテム
用途
- 細い枝・若枝・花がら摘み・弱い込み枝の除去など「まずはコレがないと始まらない」必須道具です。
失敗しない選び方ポイント
刃の素材
- ステンレス製・・・錆びにくくお手入れラク
- 高炭素鋼・・・切れ味抜群(ややサビやすいがプロ好み)
グリップ形状
- 手のひらにフィットするカーブ形状がおすすめ
- 滑り止め付きだと、長時間でも疲れにくい
安全ロック付き
- 収納時に刃が開かず、ケガ防止になる
替刃対応モデル
- 切れ味が落ちても交換でき、長く使える
ワンポイント
「切るときに“スパッ”といくかどうか」が判断基準。とくに、試し切りできるお店なら、感触も要チェックです。
剪定ノコギリ:太枝・枯れ枝はこれに任せる
用途
- 直径2cm以上の枝・固い枝・枯れ枝
- ハサミでは切れない太い枝を無理に切ると、「道具が壊れる」「枝が裂ける」「ケガをする」…とトラブルのもとに。
選び方のポイント
折りたたみ式
- 収納・持ち運びがラク&安全
曲線刃(生木向き)
- 刃が木に食い込みやすく、軽い力で切れる
片刃タイプ
- 押す動作だけで切れるから初心者向き
軽量タイプ
- 腕の疲労が少なく、作業が続けやすい
ワンポイント
「ゴリゴリ切る」感覚より、「引くと勝手に切れる」感覚のノコギリが理想です。
安全性と効率を上げる必須アイテム
剪定は“切る”よりも“守る”準備が重要。そのため、最低限、次の4つは揃えましょう。
- 手袋・・・トゲ・刃物から手を保護
- 脚立・・・高い枝の安全作業
- 保護メガネ・・・枝の跳ね返り防止
- 剪定くず袋・・・片付け時短
特に多い事故
「目に枝が当たる」「脚立から転倒」「手を切る」…これのほとんどが装備不足が原因です。
どこで揃える?まとめ買い派におすすめ
「どれを選んでいいかわからない…」そんな人には、園芸用品が一気に揃うアイリスプラザ が便利。
- 初心者向けセットあり
- 剪定バサミ・ノコギリ・脚立までまとめて購入OK
- レビューで失敗しにくい
👉 道具選びに迷ったら【アイリスプラザ公式】をチェックしてみてください。
木の種類別:剪定にベストな時期を知ろう
「剪定したのに、元気がなくなった…」その原因、時期の選び間違いかもしれません。
なぜなら、剪定はいつ切るかで…
- 木のダメージ
- 回復スピード
- 花つき・実つき
が大きく変わるからです。そのため、木の種類ごとにベストな時期は違うのが基本。
ここでは、初心者でも迷わないように「種類別×最適シーズン」をわかりやすく解説していきます。
落葉樹(モミジ・桜など)
ベスト時期:12〜2月(休眠期)
冬は葉が落ちて、枝の全体像がよく見えるため、形を整えやすいゴールデンタイムです。
この時期に剪定するメリット
- 枝の重なり・絡まりが一目でわかる
- 切りすぎを防げる
- 春の芽吹きがスムーズになる
- 病害虫の活動が少なく、感染リスクが低い
注意ポイント
- 桜は特にデリケートまので、太枝の切りすぎは樹勢低下につながる
- 「混み合っている枝」や「枯れ枝」を間引く程度に留めましょう。
ワンポイント
「透かす剪定(間引き)」が基本。そのため、切り戻しより“いらない枝を根元から取る”イメージで。
常緑針葉樹(マツ・ヒノキ)
ベスト時期:3〜4月(新芽が出る直前)
この時期は、回復力が高まり始めるタイミング。なぜなら、剪定後のダメージを最小限に抑えられるからです。
この時期が良い理由
- 新芽が動く前で、樹液の流出が少ない
- 切り口が塞がるのが早い
- 成長が安定し、形が崩れにくい
NGポイント
- 真冬の剪定は危険
→ 霜・寒さで切り口が傷みやすい - 強剪定は樹形崩れのもと
→ 枝の整理中心でOK
ワンポイント
マツは「芽摘み(みどり摘み)」を意識すると、美しい樹形を保ちやすくなります。
常緑広葉樹(ツバキ・キンモクセイ)
ベスト時期:3月後半〜4月(春の成長前)
冬の寒さを越え、樹が“動き出す直前”がベスト。
この時期に剪定する理由
- 切り口の治りが早い
- 新芽が元気に伸びやすい
- 葉焼けや枯れ込みを防げる
注意ポイント
- 強剪定はNG
→ 葉焼け・枯れ枝発生の原因に - 「形を整える程度」の軽剪定が安全
💡 花後剪定が基本の樹も多い(ツバキは花が終わってからがベスト)
絶対に避けたいNGシーズン
種類問わず、以下の時期の剪定は失敗リスクが高いです。
- 春(芽吹き直後)
→ 樹液が流れ、体力消耗 - 真夏
→ 高温+湿気で病害虫発生リスク大 - 厳冬期(霜・積雪時)
→ 切り口が凍結し、枯れ込みやすい
いつ切るか迷ったら?
「この木、今切っても大丈夫かな?」そんなときは、個別に樹種で確認するのが正解です。
剪定の基本手順:失敗しない5ステップ
剪定でよくある失敗は、「とりあえず切る」→「切りすぎた」→「樹勢が落ちる」…というパターン。なぜなら、剪定はセンスではなく手順で結果が決まるからです。
そのため、この流れ通りに進めれば、初心者でも失敗しにくく、美しい樹形に仕上げられるからです。
STEP1:不要な枝から確実に切る
まずは、迷わず切ってOKな枝から処理します。なぜなら、ここを適当にすると、後でバランスが崩れやすくなるからです。
最初に除去する枝
- 枯れ枝(完全に茶色でパキッと折れる)
- 病害枝(黒ずみ・斑点・カビ)
- 交差枝(こすれ合い、傷の原因)
- 内向き枝(樹の中心に伸びる枝)
- 下向き枝(樹形を乱す原因)
コツ
切る前に「これは確実に不要」と言える枝から処理すると、迷いが減ります。
STEP2:樹形を整える(やりすぎ禁止)
不用枝を片付けた後、ようやく「形づくり」に入ります。しかし、ここで切りすぎるのが一番多い失敗です。
意識する3つのポイント
- 自然なシルエットを保つ
- 内側に風が通るように“スカスカ感”を出す
- 伸びすぎた枝は「切り戻し」より「間引き」が基本
ワンポイント
枝を短くするより、枝ごと取るほうが木は元気になるケースが多いです。
STEP3:切り口をきれいに処理
切り方ひとつで、回復のスピードと病気リスクが変わります。
正しい処理方法
- 切り口は「斜め」に・・・水が溜まらず、腐りにくい
- 太い枝は癒合剤で保護・・・乾燥&雑菌侵入を防ぐ
- ささくれはナイフで削る・・・切り口をなだらかに整える
プロのひと手間
剪定後にアルコール消毒で刃を拭くと、病気の持ち込みを防げます。
STEP4:全体バランスを最終チェック
ここで「仕上がり」を決めます。そのため、切り終えたら必ず木から一歩離れて確認してください。
チェックポイント
- 左右のバランスは取れているか
- 上に偏りすぎていないか
- 中が混みすぎていないか
- 光と風が通るか
コツ
スマホで写真を撮ると、人の目よりバランスのズレに気づきやすくなります。
STEP5:片付け・消毒・後片付けまでが剪定
「切って終わり」はNGです。とくに、ここを怠ると病気や害虫の温床になります。
やること
- 剪定くずはすぐ処分
- 刃物はアルコール消毒
- ノコギリの樹脂汚れを拭く
- 道具は乾燥保管
プロの習慣
次に使うときに「切れ味が悪い…」とならないためにも、作業後のメンテナンスが上達の近道です。
剪定の基本フロー
作業中は、次の順番を意識してください。
- 全体を眺めてバランス確認
- 枯れ枝・病害枝の除去
- 交差枝・内向き枝を整理
- 間引き剪定で風通し確保
- 必要に応じて樹形微調整
- 切り口の保護・仕上げ
失敗を防ぐコツ:「切る前に3秒止まる」
ハサミを入れる前に必ず考えてください。
この枝を切って…
- 光は入りやすくなる?
- 風通しは良くなる?
- 全体の形はきれいになる?
すべて「YES」なら、切ってOKです。
剪定後のケアとゴミ処理:仕上げまでが剪定です
「剪定が終わった=完了」ではありません。
なぜなら、実はその後のケア次第で、木の回復スピード・病気のリスク・来年の成長が大きく変わるからです。
さらに、枝葉の始末を間違えると…
- 庭が散らかる
- 虫の温床になる
- 近所トラブルになる
ことも…。
そのため、剪定後は「木のケア」と「ゴミ処理」をセットで行うのが正解です。
剪定後のお手入れ:木を“回復モード”に切り替える
剪定は木にとって小さな外科手術のようなもの。そのため、切った直後のケアが、その後の元気さを左右します。
水やり:まずはしっかり水分補給
剪定直後は水分不足になりやすいため、根がある範囲にたっぷり水を与えましょう。とくに、夏場・鉢植えは、水切れしやすいので注意。
目安
- 鉢植え → 鉢底から水が出るまで
- 地植え → 根元がしっとりする程度
肥料:すぐ与えないのがコツ
「元気になってほしいから」と、すぐ肥料を与えるのは❌。
正しいタイミング
- 剪定から1〜2週間後。
- 新芽が動き始めてから、緩効性肥料などを少量。
- 理由・・・切った直後は根も弱っており、肥料焼けを起こす危険があります。
切り口:数日間は必ずチェック
確認ポイント
- 黒く変色していないか
- 白いカビが出ていないか
- 樹液が止まっているか
※太枝には癒合剤(ゆごうざい)を塗ると安心です。これにより、乾燥・雑菌侵入を防ぎ、治りが早くなります。
枝葉の処分方法:ただ捨てるだけじゃもったいない
剪定ごみは、大きさと量で処分方法が変わります。
一般ゴミとして出す場合
小枝・葉・細かい枝
- 自治体指定の袋に入れて「可燃ごみ」
コツ
- 短く切れば袋に収まりやすく、収集拒否されにくくなります。
粗大ゴミになるケース
太枝・幹・大量の枝
- 予約制・有料回収が多い
自治体ホームページで「剪定枝 処分方法」と検索がおすすめ。
再利用できるアイデア
「捨てる前に、使えないかな?」意外と使い道はあります。
コンポスト
細かく刻んで生ゴミと混ぜれば、土に還る天然の堆肥に。
薪・焚き付け
乾燥すれば、アウトドア用の燃料に。
マルチング材
花壇や木の根元に敷けば…
- 乾燥防止
- 雑草予防
- 土壌温度の安定
に役立ちます。
焚き火・野焼きは要注意!
落ち葉や枝を「燃やせばいい」と思いがちですが、多くの地域で法律・条例で禁止されています。とくに、煙・ニオイ・火災原因になり、近隣トラブルに発展することも…。
そのため、必ず
- 自治体ルールを確認
- 指定の回収方法に従う
剪定は「切って終わり」ではありません
このように、剪定の本当の完成は…
- ケア
- 片付け
- 再利用 or 適切処分
まで終えて、初めて「成功」です。少しの手間で、木は元気になり、庭はきれいに保てます。
剪定が不安な方へ:業者と教室を上手に使おう
「失敗したくない」「高木が怖い」「時間が取れない」そんなときは、無理せず“プロに任せる”か“学んで自分でできるようにする”のが近道です。
そのため、あなたに合う方法を、目的別に選んでみましょう。
プロに任せたい方(安全・時短・仕上がり重視)
こんな方におすすめ
- 高い木/太い枝がある
- 電線・塀の近くで危険
- 忙しくて時間がない
- 見た目もきれいに整えたい
おすすめ業者
ポイント
無料見積もりで“2~3社比較”
同じ内容でも、料金・対応・提案が変わることがあります。そのため、比較するだけで納得度がぐっと上がります。
自分でできるようになりたい方(長期的に節約・スキルアップ)
「毎年業者は高い」「自分で管理できるようになりたい」という方は、プロの技を一度習うのが最短ルート。
ゼロから学べる実践教室
-
玉崎弘志の剪定教室・・・
基本の切り方・道具の使い方・樹種別のコツまで、実演で学べます。
こんな人におすすめ
- 毎年自分で剪定したい
- 切る位置・量の判断を身につけたい
- 将来のメンテ費を減らしたい
迷ったらこの選び方
- 今すぐ安全に終わらせたい・・・業者
- これからずっと自分でやりたい・・・教室
- 仕上がりも学習も両方ほしい・・・まず業者、次に教室
このように、剪定は「我慢」する作業ではありません。そのため、プロに任せる・学ぶという選択で、庭はもっとラクに、きれいになります。
まとめ:剪定ひとつで庭の印象は大きく変わる
いかがでしたか?
剪定は、ただ枝を切る作業ではありません。そのため、時期・道具・切り方を少し意識するだけで、木は元気になり、庭は驚くほどきれいに変わります。
要点まとめ
- 時期で成否が決まる
- 道具選びが重要
- 枝の見極めがカギ
- 切り口は必ず保護
- プロ併用も選択肢
今日からできる行動
- 木の種類を確認
- 時期をチェック
- 道具を準備
- 不安なら相談
準備と相談から始めよう
- 「道具が足りない」
- 「どこまで切っていいかわからない」
そんなときは、公式サイトで設備とサービスを確認するのが近道です。
関連記事:
- 剪定、伐採なら「お庭マスター」
- 【剪定業者の魅力♪】剪定業者に依頼すべき5つの理由
- 【庭が劇的に変わる!】評判の庭木手入れ業者を今すぐチェック
- 【庭木の剪定を学習】庭の美を引き出す剪定術
- お庭のメンテナンスが簡単に!【お庭110番】の魅力
- プロに任せる庭の手入れのメリットと方法
- 【庭木の片付け方法】効率的な手順と注意点
- 【全国対応剪定110番!】庭木の剪定をプロがスピード解決

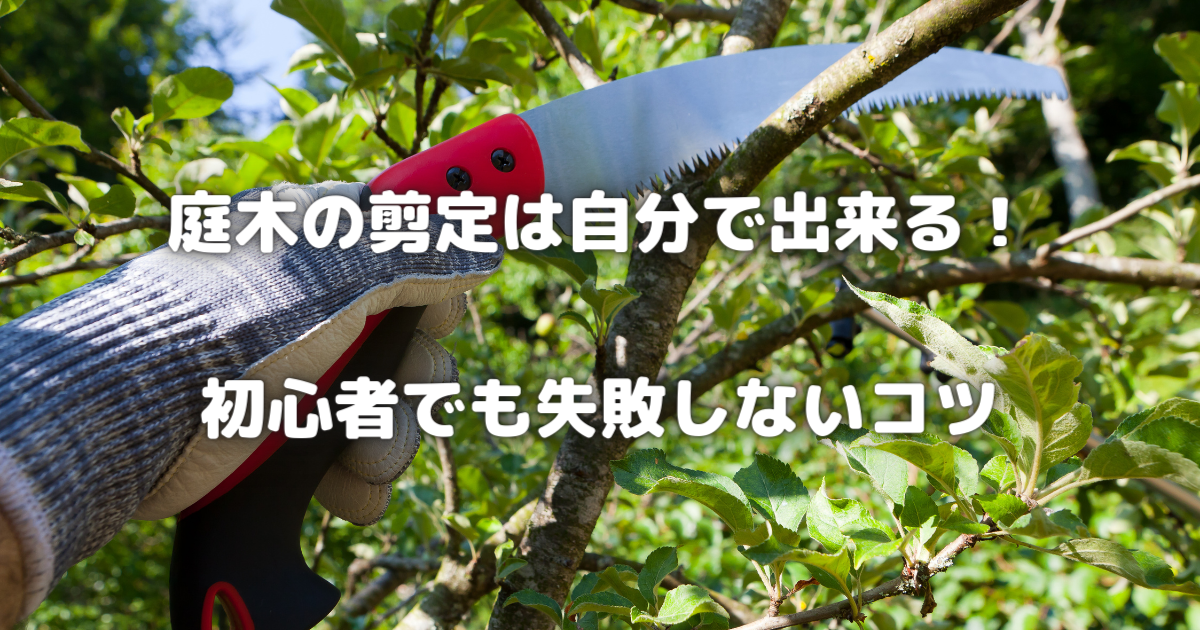






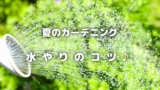




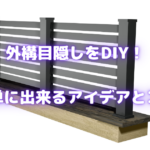
コメント