塀を最小限にして光と風を取り込むオープン外構。
この記事では、メリット・注意点、目隠し/植栽/照明/家具の実例、失敗しない設計手順と予算の考え方を初心者向けにやさしく解説していきます。

お庭のリニューアルを考えている方は、ぜひ参考にしてください。![]()
オープン外構とは?メリット・デメリットを事前にチェック
「オープン外構」という言葉を耳にしたことはありますか?
最近は、塀や門をあえて作らず、街並みと自然につながるデザインが人気を集めています。とくに、開放感やおしゃれな雰囲気が魅力ですが、一方でプライバシーや防犯面で不安を感じる人も少なくありません。
ここでは、オープン外構のメリット・デメリットをわかりやすく整理し、後悔しないためのポイントを事前にチェックできるように解説していきます。
オープン外構の定義
「オープン外構」とは、塀やフェンスをできるだけ使わず、道路や街並みと“ゆるやかにつながる”デザインのこと。
とくに、閉鎖感をなくし、開放的でおしゃれな印象を演出できるため、最近人気が高まっています。
メリット
開放感と採光・通風の向上
- 遮るものが少ないため、日差しや風が家全体に届きやすく、室内も明るく快適に。
- 圧迫感のない広々とした雰囲気を楽しめます。
街並みとの調和でスタイリッシュに
- 道路や近隣の住宅との境界をあえて緩やかにすることで、街並みに自然に溶け込み、洗練された印象を与えます。
初期コストを抑えやすい
- 高い塀や門扉を設けない分、資材費・施工費が少なく済むため、予算を抑えつつデザイン性を高められます。
デメリットと対策
視線や防犯が気になる
- 道路からの視線が入りやすいため、プライバシーや防犯に不安を感じることも。
👉 対策・・・
低木・スリットフェンス・足元灯を組み合わせて「見えにくいゾーン」を作る。
境界線があいまいになりがち
- 公私の境がぼやけると、来客や近隣の人がどこまで入って良いのか迷うことも。
👉 対策・・・
舗装材や砂利を切り替えて「見えない境界」をデザインで表現する。
維持管理の手間
- 開放的な分、雑草や落ち葉が入り込みやすいのが難点。
👉 対策・・・
防草シート+ローメンテ植物で雑草対策をし、掃除や手入れを最小限に。
このように、オープン外構は「街とつながる開放的なデザイン」を楽しめる一方で、防犯やメンテナンス面の工夫が欠かせません。
そのため、事前にメリット・デメリットを理解し、対策を盛り込むことで、快適でおしゃれな住まいを実現できます。

まずは設計の基本:失敗しない5つのチェック
外構工事は一度完成すると大きな修正が難しいため、最初の設計段階で「押さえるべき基本」を知っておくことが重要です。
ここでは、プロが必ずチェックする5つのポイントを紹介していきます。
1. 視線計画
外構は外からの見た目だけでなく、家の中からどう見えるかも大切です。
とくに、ソファやダイニングなど「主観席」からの視線を意識して設計すると、日常の景色がぐっと心地よくなります。
👉 例えば、リビングから見える場所にシンボルツリーを置くと、四季の変化を楽しめる“借景”になります。
2. 動線
家と外構は「毎日の動きやすさ」で快適さが決まります。
- 玄関⇄駐車場⇄庭はできるだけ直線的に
- 踏み石や飛び石はピッチ60〜70cmが歩きやすい基準
そのため、動線を無視すると「雨の日に遠回りで不便」「駐車場から荷物が運びづらい」といった不満が残りやすいので、図面段階でシミュレーションするのが鉄則です。
3. 排水
「水が溜まらない設計」は外構の寿命を左右します。
- 屋根の雨落ち位置を考慮
- 勾配をつけて自然排水
- 必要に応じて暗渠(あんきょ)排水を設置
とくに、水はけが悪いと、芝生が蒸れて枯れたり、タイルが黒ずんだりとトラブルの元になるので、必ず事前に確認しましょう。
4. ゾーニング
庭を「見せるスペース」と「使うスペース」に分けると、デザインと実用性のバランスが取れます。
- 見せる庭・・・芝生や植栽で彩りを演出
- 使う庭・・・砂利・タイル・ウッドデッキでメンテ性を重視
そのため、素材を切り替えることで、自然に境界が生まれ、暮らしやすい空間に仕上がります。
5. 予算
外構は見積もり金額だけで決めると失敗しやすいポイントです。
- 本体工事費に+10〜20%の予備費を組み込む
- 2〜3社で相見積もりを取り、仕様・保証・アフターサービスまで比較する
とくに、「安いから」と選んでしまうと、工事後に追加費用が発生したり、メンテに不安が残ることもあります。
デザインアイデア:開放感を損なわず“ちょうど良い目隠し”をつくる
オープン外構の魅力は開放感です。しかし、その一方で「視線が気になる」「落ち着けない」と感じることも…
そんなときに役立つのが、ほどよい目隠しをつくるデザインテクニックです。そのため、完全に閉じるのではなく、視線をやわらかく遮ることで、外からの印象もスタイリッシュに仕上がります。
(1) 植栽で抜け感のあるスクリーンをつくる
道路側には株立ち落葉樹+常緑低木
- 夏は葉が茂り日差しや視線をカット、冬は枝のシルエットが軽やかで季節感も演出。
- 常緑低木を組み合わせれば、一年を通して程よい目隠し効果が得られます。
足元はタマリュウやヤブランでラインを描く
- 地被植物でラインを入れると視覚的に境界がはっきりし、雑草抑制にも効果的。
- デザイン性とメンテナンス性を両立できます。
(2) スリットフェンス/ルーバーフェンスをシーンで使い分け
玄関前は縦スリット
- 適度に隙間があり、上品で軽やかな目隠しに。
- 玄関まわりの印象をモダンに引き締めます。
テラス脇は可動ルーバー
- 風や光を通しながら、必要に応じて角度を変えて視線を調整。
- 屋外リビングやプライベートな庭空間にぴったりです。
(3) 素材の“引き算”でモダンに仕上げる
素材は2〜3種類に統一
- 木・石・金属といった異素材を多用しすぎるとごちゃついた印象に。
- 選ぶ素材は2〜3種類に絞り、統一感を出すのがポイントです。
仕上げは砂利+コンクリート見切り
- シンプルな砂利敷きをコンクリ見切りで引き締めると、外構全体に“モダンで整った印象”を与えられます。
このように、「視線を完全に遮らない」ことが、オープン外構を美しく保つコツです。
そのため、植栽・フェンス・素材の組み合わせで、ちょうど良い目隠しを実現することで、開放感を残しながらプライベート性も確保できます。
屋外リビングをつくる:ウッドデッキ/テラス/家具の選び方
庭を「もうひとつのリビング」に変えることで、家時間の楽しみ方がぐっと広がります。
とくに、ウッドデッキやテラスに家具を配置するだけで、朝はコーヒー、夜はお酒や星空観賞といった“外での暮らし”が実現できます。
ウッドデッキ・テラスのポイント
室内とつなげて段差を最小化
- 床レベルを室内と揃えると、出入りがスムーズになり、まるでリビングが外に広がったような一体感が生まれます。
- バリアフリー性も高まり、家族みんなが使いやすい空間に。
樹脂デッキは初心者におすすめ
- 天然木は雰囲気が抜群ですが、腐食や定期メンテナンスが必要。
- 対して樹脂デッキは腐らず、掃除も簡単で初心者向け。
- 初期投資後の維持コストが低いのも魅力です。
ガーデンファニチャーの選び方
ソファ&ローテーブルで“外リビング感”を演出
- 屋外対応のクッション付きソファを置けば、くつろぎの質が一気に向上。
- 耐候性のある生地を選べば、雨や紫外線にも強く長持ちします。
- ローテーブルを添えれば、読書やティータイムも快適。
ハンモックやデッキチェアで“非日常”をプラス
- 可搬型のハンモックや折りたたみ式のデッキチェアは、使わないときに片付けやすいのがメリット。
- 休日の昼寝や星空観賞など、特別なリラックスタイムを演出できます。
このように、屋外リビングは、「デッキやテラス」と「家具選び」のバランスで居心地が決まります。
そのため、段差をなくしてリビングの延長にし、快適な家具を配置すれば、毎日がちょっと贅沢に。そして、小さな工夫から始めれば、庭やベランダが“もうひとつのリビング”に変わります。
夜も“映える”外構:照明計画の基本
外構デザインは昼だけでなく、夜の見え方でも印象が大きく変わります。とくに、光の当て方ひとつで、庭やファサードは幻想的にも安心感のある空間にもなります。
ここでは、外構を「夜でも映える空間」にする照明計画の基本を紹介していきます。
光のレイヤーをつくる
面の光(ポールライト/スタンドライト)
- 広い範囲をほんのり照らす光。
- 玄関アプローチや花壇沿いに設置すると、空間全体に落ち着きが生まれます。
点の光(スポットライト/グレアレスライト)
- 見せたい樹木やオブジェに的確に光を当てることで、夜の庭にドラマチックな陰影を演出。
- 光が強すぎない「グレアレス(眩しさカット)」タイプなら、上品な仕上がりに。
👉 面+点の光を重ねることで、奥行きと立体感が出て“ホテルライクな夜景”が実現します。
演出と実用を両立する
株元をナナメから照らす
- シンボルツリーや低木の株元に光を当てると、枝や葉が立体的に浮かび上がり、昼間とは違う美しさを楽しめます。
足元灯で安全&防犯
- アプローチや階段に控えめな足元灯を入れると、転倒防止になり、防犯性も向上。
- 光のリズムで歩きやすくなり、来客への“おもてなし感”も演出できます。
ソーラーライトを上手に活用
配線不要で設置がラク
- 電気工事が不要なため、DIYでも気軽に設置可能。
- 庭のアクセントやサブ照明として活躍します。
並べすぎないのがコツ
- 動線沿いにソーラーライトを“等間隔でズラッと”並べると、空港の滑走路のように単調に見えることも。
- 植栽の間やポイントごとに配置して、自然なリズムをつくりましょう。
このように、夜の外構照明は、「面の光+点の光」+「安全性」+「手軽さ」をどう組み合わせるかがポイントです。
そのため、デザイン性と実用性を両立させることで、昼とは違う表情を持つ“映える庭”を楽しめます。
アクティビティで“使う庭”へ:BBQ/読書/ガーデニング
庭はただ眺めるだけでなく、使う場所に変えることで毎日の楽しみがぐっと広がります。そのため、大がかりな工事をしなくても、ちょっとした工夫でアウトドアリビングのように活用できます。
ここでは、シーン別のアイデアを紹介していきます。
朝コーヒーで一日のスタートを整える
東向きの軽やかな朝日を取り込む場所にチェア1脚
- 朝日を浴びながらコーヒーを飲む習慣をつくるだけで、気持ちが前向きに整います。
- 庭の一角を“自分専用のカフェ席”にする感覚で、日々のルーティンに取り入れてみましょう。
BBQ/ホームパーティで家族や友人と楽しむ
耐熱マットを敷いて安全に
- ウッドデッキや芝生を焦がさないために必須。
- 手軽に敷ける耐熱マットを用意しましょう。
消火用の水を常備
- バケツやホースを近くに置けば、安心して火を扱えます。
照明やテントで夜も快適に
- 照明を組み合わせれば雰囲気アップ、サンシェードを活用すれば日中も快適に過ごせます。
ガーデニング入門で“育てる楽しみ”をプラス
プランター3鉢からスタート
- ハーブ・草花・小さな野菜の3種類を選べば、収穫・観賞・香りと三拍子そろって楽しめます。
初心者におすすめの場所
- 日当たりが良く、毎日視線が届く玄関前やデッキ周りがおすすめ。
- 水やり忘れの防止にもつながります。
リゾート感を演出して“非日常”を楽しむ
植栽・照明・ガーデンファニチャーを工夫するだけで、庭がプチリゾート空間に早変わり。
そのため、夜はライトアップで幻想的に、休日はデッキチェアやハンモックでリラックスすれば、旅行に行かなくても非日常を味わえます。
このように、庭は「使い方」を工夫するだけで、毎日の暮らしを豊かにしてくれる空間になります。
そして、朝はコーヒー、昼はガーデニング、夜はBBQやライトアップ。小さな一歩から始めて、庭を“暮らしのステージ”に変えてみましょう。
目隠し・防犯・プライバシーの実務ポイント
外構計画で見落とされがちなのが、「目隠し」と「防犯」と「プライバシー」のバランスです。なぜなら、完全に閉じてしまうと圧迫感が出ますが、オープンすぎると安心感が失われてしまうからです。
ここでは、実際の生活に役立つ“実務的な工夫”を紹介していきます。
視線対策は「高さ」と「部分的な遮り」が鍵
基準は立った時の目線=約1.5m
- この高さを意識して、フェンスや植栽で「視線が通りにくいライン」だけを遮るのが効果的。
全部を塞がないのがポイント
- 完全に閉じると暗く・窮屈な印象になるため、抜け感を残して圧迫感を防ぎましょう。
👉 例・・・
玄関横に縦格子のスリットフェンス+株立ちの植栽を組み合わせると、視線はカットしつつ風と光を通せます。
防犯は「音」と「光」で気づかせる
防犯砂利で接近を音で察知
- 足を踏み入れると“ジャリッ”と音が鳴る防犯砂利を敷けば、不審者も心理的に近づきにくくなります。
センサーライトで不意を突く
- 人感センサー付きライトは、夜間の侵入を威嚇する効果あり。
- 防犯砂利と組み合わせれば、音と光のダブルガードで安心です。
プライバシーと利便性の両立
番地プレートはしっかり見える位置に
- 宅配業者や来客が迷わず見つけられるよう、ポストやインターホン付近に配置。
宅配・来客導線は直線的に
- 玄関までのアプローチを直線的にすると、防犯カメラやセンサーライトの死角が減り、スムーズな動線が確保できます。
このように、目隠し・防犯・プライバシーは、「高さを限定的に遮る」「音と光で威嚇」「利便性を損なわない」の3つを意識することがポイントです。
そのため、美観を保ちながら安心できる外構を実現するには、このバランス設計が欠かせません。
予算と見積もり:ホームセンター/通販/外構業者の使い分け
外構にかける予算を考えるとき、「どこまでDIYで対応するか」「どこからプロに任せるか」の線引きがとても重要です。
そのため、うまく使い分ければ、コストを抑えつつ仕上がりの満足度も高められます。
ホームセンター/通販(DIY向き)
向いているもの
- 小規模な照明、ガーデン家具、鉢植えやシンボルツリーなどの植栽。
- 設置や交換が比較的簡単で、失敗してもリスクが小さいもの。
コスト感
- 低〜中価格帯で選択肢が多く、比較もしやすい。
- キャンペーンや送料無料を活用すればさらにお得。
注意点
- 送料・返品条件・在庫状況の確認は必須。
- とくに、植栽や大型資材はサイズ感を誤ると再購入の手間がかかります。
👉 気軽に始めたい人はDIYから着手すると◎
外構業者(プロ施工向き)
向いているもの
- 駐車場の土間コンクリート、排水工事、電気工事、塀やフェンスなどの構造物。
- 安全性や耐久性が求められる部分は必ずプロに任せるのが安心です。
コスト感
- 中〜高価格帯ですが、その分「施工保証」「図面による明確な仕様確認」「美しい仕上がり」が期待できます。
依頼時のポイント
- 相見積もりは2〜3社に依頼
- 図面・仕様書・照明回路の有無まで比較
- 保証内容やアフターフォローを必ず確認
このように…
- DIYで費用を抑えやすい部分 → 照明・家具・植栽
- 外構業者に任せるべき部分 → 構造物・排水・電気工事
すべてをDIYにするのではなく、「安全性が必要な部分は業者」「雰囲気づくりはDIY」と切り分けることで、コストと仕上がりのバランスが最適化できます。
施工ステップ(初心者向け):小規模ゾーンの例
初めて外構づくりや庭づくりに挑戦するなら、いきなり大規模に取りかかるよりも「一角を小さく仕上げる」ことから始めるのが安心です。
ここでは、初心者でも取り組みやすい小規模ゾーンの施工ステップをわかりやすく解説していきます。
1. 現況採寸
計測するポイント
- 敷地の広さ、高低差、既存の配管やマンホール位置など。
理由
- 実際にサイズを測らずに作業を始めると、「家具が入らない」「排水口をふさいでしまった」などのトラブルに直結します。
👉 メジャーやスマホの測定アプリを活用すると簡単です。
2. ゾーニング
3つに分けて考える
- 見せるスペース(植栽・ライトアップ)
- 使うスペース(テーブル・チェア・BBQ)
- 通るスペース(アプローチや動線)
コツ
- 紙にラフスケッチして、ざっくりと区分を描くとイメージが定まります。
3. 下地づくり
基本の流れ
- 雑草除去 → 整地(凸凹をなくす) → 防草シート → 砂利敷きや舗装
ポイント
- 下地を丁寧にやるかどうかで、見た目と維持管理の手間が大きく変わります。
👉 とくに、雑草は根からしっかり取り除くことが大切です。
4. 主役を決める
例:シンボルツリー or ガーデンソファ
- ひとつ“主役”を置くと全体がまとまり、空間の方向性がはっきりします。
効果
- 余計な装飾を足さなくても、主役があるだけで「計画された庭」に見えるのがポイントです。
5. 照明/電源の確保
コンセント位置や配線を事前に確認
- 照明や電動工具を使うなら必須。
- 延長コードに頼るより、屋外コンセントを増設すると便利です。
ソーラーライトの活用
- 配線工事不要で設置が簡単。
- 動線沿いやシンボルツリーの足元に置くと効果的です。
6. 仕上げ
アクセント植栽や小物で雰囲気UP
- 鉢植えやガーデンライト、小物を加えるだけで“生活感”が抑えられ、完成度が上がります。
最後は夜の点灯チェック
- 昼と夜で印象は大きく変わるため、夜にライトアップして安全性と雰囲気を確認しましょう。
このように、外構や庭づくりは「採寸→ゾーニング→下地→主役→照明→仕上げ」の流れを押さえれば、初心者でも小さなスペースから気軽に始められます。
そのため、まずは自分の庭の一角を選んで、少しずつ“理想の外構”を形にしてみましょう。
よくあるQ&A
オープン外構に興味はあるけれど、「防犯面は大丈夫?」「目隠しはどこまで必要?」といった疑問を持つ方は多いものです。
ここでは、読者からよく寄せられる質問に答えながら、不安を解消しつつ実際に役立つポイントを紹介していきます。
Q. オープン外構は本当に防犯上不利?
A. 必ずしも不利とは限りません。
「塀がない=侵入しやすい」と思われがちですが、実際には“見通しの良さ”が防犯抑止力になるケースも多いのです。
とくに、高い塀で囲ってしまうと、かえって死角が増え、不審者が潜みやすくなることもあります。
- 死角を作らないレイアウト(植栽や物置の配置に注意)
- 足元灯で夜も人の気配を演出
- 人感センサーライトや防犯砂利で“驚かせる仕掛け”を追加
これらを組み合わせれば、開放感を保ちながら安心できる防犯対策が可能です。
Q. 目隠しはどこまで必要?
A. 立ったときの視線(約1.5m)をコントロールするだけで十分です。
全面的に遮ると閉塞感が出て、せっかくのオープン外構が台無しになってしまいます。そのため、ポイントは“部分遮蔽”。
- 玄関やリビングの正面だけスリットフェンスを設置
- テラス脇に植栽スクリーンを配置
- 足元や腰高レベルはオープンにして光と風を通す
こうすることで、外観のスタイリッシュさと室内のプライバシー確保を両立できます。
👉 まとめると、オープン外構は「死角を減らす工夫」と「視線を部分的に遮る設計」で、快適さと安心感を同時に実現できるデザインです。
まとめ:開放感×目隠しのさじ加減が成功の鍵
いかがでしたか?
要点
- 開放感・採光・通風を最大化しつつ、部分目隠しでプライバシー確保
- 素材は2〜3種に統一、照明は面+点のレイヤー
- 予算は本体+10〜20%の予備費、相見積もりで仕様・保証まで比較
- ローメンテ植物+防草で維持の手間を最小化
今日からできる行動
- 室内の主観席から見える三角構図をラフスケッチ
- 目隠しが必要な高さ・位置をメモ(立位1.5m基準)
- 照明(仮置き)→夜の点灯テストで光の当て方を確認
- 予算感を掴むため2〜3社に相見積もり依頼
オープン外構は、「開放感を活かしつつ、必要な部分だけ目隠しする」ことで、快適さと安心感の両立が叶います。そのため、まずはスケッチや簡単な照明チェックから始めてみましょう。
そして、次のステップは“比較”です。公式サイトで詳細を確認して、あなたの暮らしに合った外構計画を立ててみてください。
また、外構業者をお探しなら以下のリンクをチェックしてください!
関連記事:
- 外構工事の「ロイヤルガーデン」とは?
- 【初心者向け!】自宅でできるロックガーデンの作り方ガイド
- 【外構をやり直したい!】失敗しないためのポイント
- 外構でよくある失敗例とその対策
- 初心者でも簡単!ドライガーデンの作り方
- 【外構砂利の選び方と魅力を徹底解説!】おしゃれな庭作りの秘訣
- 【外構目隠しDIY完全ガイド】初心者から上級者まで楽しめるアイデアと実践コツ
- 「外構・エクステリアパートナーズ」で賢く外構工事予算を管理し、夢のお家を実現
- 【外構に芝生を!】費用を節約しながら素敵な庭を作る方法
- エクステリアと外構の違いを徹底解説!
- 【地中海風ガーデン!】初心者でも簡単におしゃれな庭づくり




















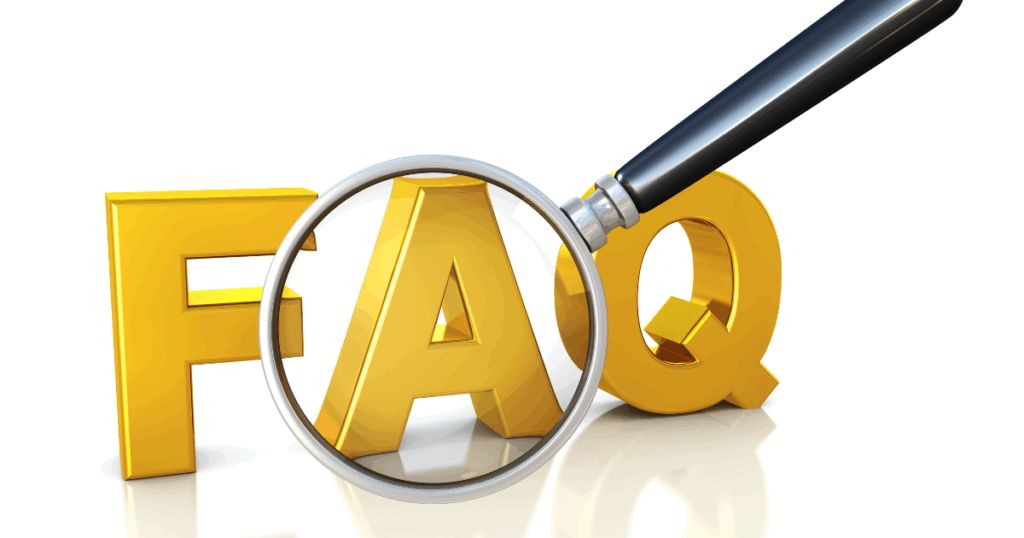


コメント