庭いじりで避けて通れないのが「虫・害虫」の問題。なぜなら、放置すると植物が弱ったり、見た目が悪くなるだけでなく、人に害を及ぼすこともあるからです。
この記事では、庭の虫対策の基本(原因・予防・駆除・プロ依頼)を初心者にもわかりやすく解説していきます。また、薬剤に頼りすぎないナチュラルな方法も紹介します。

庭の虫対策は、とても重要なことです。ぜひ参考にしてください。
庭の虫対策が大切な理由
庭で虫(害虫)が発生すると、見た目が悪くなるだけでなく、植物・暮らし・安全面にまで影響が広がります。
例えば…
- 新芽や根が食べられ、植物の生育が止まる・最悪は枯れてしまう
- 葉や花に穴や変色が出て、「手入れしているのに汚く見える」
- ハチ・ムカデ・毛虫など、刺す・咬む虫は人やペットにケガのリスク
- ゴキブリやコバエが発生し、家の中まで侵入するなど衛生面のトラブル
これらは、放置すると被害が連鎖的に広がるのが虫トラブルの怖いところ。
だからこそ大切なのは、「被害が出てから慌てて駆除する」のではなく、「虫が来る原因を知り、予防しつつ早めに対処すること」です。
そして、庭の虫は、実は…
- 水のたまり
- 風通しの悪さ
- 枯れ葉・雑草
といった庭環境の小さな乱れをきっかけに増え始めます。
そのため、まずはどんな虫が、どんな被害をもたらすのかを知ること。それが、薬に頼りすぎず、ムダな対策を減らす近道でもあります。
このあと、代表的な庭の害虫とそれぞれの対処法を分かりやすく解説していきます。
STEP1:庭にいる害虫の種類を特定しよう
虫対策でいちばん多い失敗が、「正体が分からないまま、とりあえず薬をまく」こと。
なぜなら、実は害虫によって
- 効く対策
- 逆効果になる行動
- 放っておいていいケース
がまったく違うからです。
だから、最初にやるべきなのは、「今、庭にいる虫は何者なのか?」を知ること。そして、難しく考える必要はありません。まずは、見た目と被害の特徴から絞り込みましょう。
代表的な庭の害虫とその被害
アブラムシ(アリマキ)
- 新芽や葉の裏にびっしり群がって樹液を吸う
- 葉が縮れる、ベタつく、成長が止まるなどの症状が出やすい
- 植物が弱り、ウイルス病などの病気にもかかりやすくなる
また、アブラムシはアリと共生することで有名です。そのため、庭でアリが不自然に増えていたら、その先にアブラムシが潜んでいるサインかもしれません。
カイガラムシ
- 茎や葉に白〜茶色の小さな殻状の塊としてこびりつく
- 一見ゴミにも見えるため、気づくのが遅れがち
- 栄養を吸われ、枝葉が徐々に弱っていく
さらに厄介なのが、排泄物(甘露)。これが原因ですす病を引き起こし、葉が黒く汚れて光合成ができなくなります。
そして、気づいたときにはかなり進行しているケースが多い害虫です。
ゴキブリ
- 植物を食べるよりも、落ち葉・腐葉土・生ゴミなどの有機物を好む
- 見かけるだけで強い不快感があり、家族のストレス源になりやすい
- 庭をすみかにすると、室内への侵入経路になることも
とくに、「庭にいるだけだから大丈夫」と放置すると、知らないうちに家の中で遭遇…ということも少なくありません。
このほかにも…
- ナメクジ(葉や花を食害)
- ヨトウムシ(夜に活動し、朝には葉が消えている)
- ハダニ(葉の色抜け・細かな斑点)
など、庭には見えにくい害虫がたくさん潜んでいます。
害虫の調べ方:スマホ・お店・専門サービスを活用
スマホで撮ってオンライン検索
- 虫や被害箇所をできるだけアップで撮影
- 画像検索や園芸サイト、害虫図鑑と照合
- 農薬メーカーや自治体の公式サイトは情報の信頼度が高め
「名前が分からない=対策できない」と思われがちですが、今はスマホが最強の害虫図鑑です。
園芸店・専門窓口に相談
- 被害を受けた葉や虫の写真 or 実物(袋に入れる)を持参
- 園芸店スタッフに見てもらう
- 地域の農業普及センター・市町村の相談窓口も意外と頼れます
また、プロの目線が入ることで…
- 「それ、実は様子見でOKですよ」
- 「今の時期はこの対策がベストです」
といったムダのない判断ができます。
記録を残すクセをつける
- 虫の種類・色・大きさ
- 発生場所(葉裏/茎/土の上/根元など)
- 発生した時期・季節
そして、写真+簡単なメモを残しておくだけで、次に同じ被害が出たとき、
- 「あ、前と同じやつだ!」→ すぐに正しい対策ができる
という安心感につながります。
このSTEPのゴール
「正体不明の虫」を「対処法が分かる相手」に変えること。
そして、次のSTEPでは、「なぜその害虫が庭に集まってくるのか?」という原因と環境の改善ポイントを見ていきましょう。
STEP2:【虫が発生する原因を知る】「環境」を整えるのが一番の予防
「虫を見つけるたびに駆除しているのに、また出てくる…」実はこれ、庭の環境そのものが“住みやすい家”になっているサインかもしれません。
とくに、害虫は…
- 湿気が多い
- エサが豊富
- 隠れ場所がある
こうした条件がそろうと、自然と集まってきます。つまり、発生の原因を断たない限り、どれだけ駆除してもイタチごっこ。
ここでは、庭で害虫が増えやすい代表的な原因と、今日からできる改善ポイントを見ていきましょう。
原因1:多湿な庭は虫の温床になりやすい
多湿の何が問題?
庭がジメジメしていると、次のトラブルが起こりやすくなります。
- 土や葉にカビや病原菌が繁殖しやすくなる
- ナメクジ・アリ・ムカデなど、湿気を好む害虫が増える
- 根が傷み、植物が弱る → 害虫に狙われやすくなる
とくに…
- 雨のあとに水たまりが残る
- 晴れても土がいつも乾ききらない
こんな庭は要注意。なぜなら、虫にとっては、「住み心地抜群の環境」だからです。
多湿対策のポイント
難しい工事をしなくても、できることは意外と多いです。
- 庭にゆるい勾配をつけ、水が自然に流れるようにする
- 砂利やバークチップを敷いて排水性+乾きやすさをアップ
- 排水口・側溝まわりの落ち葉や土詰まりを定期的に掃除
- 水やりは朝に行い、夜まで湿った状態を残さない
とくに、水やりは「多すぎ」も「少なすぎ」もトラブルのもと。そこで役立つのが…
👉 自動水やりシステム
タイマー管理で、やりすぎ・水不足の両方を防ぎ、庭の湿度を安定させやすくなります。
原因2:虫を呼び込みやすい植物配置
特定の植物には「つきやすい虫」がいる
害虫は、好きな植物に一直線です。
- バラ・・・アブラムシ
- キャベツ・・・ヨトウムシ・コナガ
- ナス・・・ハダニ
とくに、こうした植物を、同じ場所に密集させて植える(単植)と、虫にとってはまさに食べ放題ビュッフェ状態。そして、一度気づかれると、被害が一気に広がります。
コンパニオンプランツで「虫が嫌がる香り」をプラス
そこで活躍するのが、コンパニオンプランツ。
- ラベンダー・・・アブラムシ避け
- ミント・・・アリ・コナガ避け
- マリーゴールド・・・土中害虫・アブラムシの抑制
とくに、香りの強いハーブや花を組み合わせることで…
- 害虫が寄りつきにくくなる
- 被害が広がりにくくなる
- 見た目もおしゃれになる
と、一石三鳥の庭づくりができます。そのため、「防虫=薬」ではなく、植え方と配置で守る庭を目指しましょう。
STEP2のポイントまとめ
- 害虫は「環境が整っている庭」に集まる
- 湿気対策は、虫・病気・植物の弱りを同時に防げる
- 植物配置を工夫すれば、薬に頼らない予防ができる
そして、次のSTEPでは…
それでも発生してしまったときの「安全&効果的な対処法」を解説していきます。とくに、「薬は使いたいけど、なるべく安全にしたい」方は必見です。
STEP3:【総合的な虫対策】3つの方法を組み合わせよう
害虫対策でよくある失敗が、「強い薬に一発で頼ろうとすること」。たしかにその場では効きますが…
- 天敵もいなくなる
- 耐性を持つ虫が増える
- 逆に次の被害が大きくなる
といった負のループに入ることも少なくありません。
そのため、おすすめなのは…
- できるだけ自然に
- 足りなければ人の手で
- 最後の手段として薬剤
この順番で考えること。
つまり…
- 生き物(天敵)に助けてもらう
- 手や道具で物理的に取り除く
- 必要なときだけ薬剤を使う
この組み合わせなら、庭の生態系を守りながら、無理なく害虫をコントロールすることができます。
① 生物的防除:天敵を味方につける
主な天敵と、食べてくれる害虫
- テントウムシ・・・アブラムシ
- クモ・・・コバエ・小さな害虫全般(夜に活発)
- カマキリ/ヒラタアブの幼虫・・・ハダニ・アブラムシ など
このように、「虫=全部悪」ではありません。とくに、天敵は、あなたの庭を守ってくれるパートナーです。
天敵が暮らしやすい庭づくりのコツ
- 草木をすべて刈り取らず、一部に“隠れ家ゾーン”を残す
- 農薬を多用しない(天敵まで減ってしまう)
そして、花壇や畑に…
- ミント
- ディル
- フェンネル
などのハーブを混植して、ヒラタアブ・テントウムシを呼び込む。このように、「完璧にきれいな庭」より、少し自然が残る庭のほうが、虫トラブルは起きにくいのです。
② 機械的防除:手・水・ネットでシンプルに対処
代表的な方法
- 虫や卵を手で摘み取る(軍手・ピンセットがあると安心)
- ホースの水でアブラムシを吹き飛ばす
- 黄色粘着シートでアブラムシ・コナジラミを捕獲
- 防虫ネットで野菜や花を覆い、物理的に侵入を防ぐ
このように、どれも地味ですが、「早い・安全・確実」な対処法です。
効果的なタイミング
- 早朝・夕方は虫の動きが鈍く、作業しやすい
- 「なんか怪しいな?」と感じた初期段階がベスト
とくに、被害が広がる前に対応できれば、薬を使わずに済むケースがほとんどです。
③ 化学的防除:殺虫剤・忌避剤は「必要最小限」に
どうしても被害が止まらない場合は、ピンポイントで薬剤を使うのも正解です。
駆除剤の種類と特徴
ピレトリン系
- 天然由来成分ベース
- アブラムシ・ハダニなどに効果
- 分解が早く、比較的安全性が高いとされる
ニームオイル
- 植物由来オイル
- 殺すというより、成長・繁殖を妨げるタイプ
- 環境に配慮しながら虫の数を抑えたい人向け
使用時の注意点(超重要)
- 必ずラベルを読み、希釈倍率・回数を守る
- 被害が出ている部分に限定して散布
そして、風のない日を選び…
- 近所の洗濯物
- 子ども・ペット
への影響に配慮することが大切です。そして、使用後は手洗い・使用器具の洗浄も忘れずに!
とくに、「たくさん使えば効く」はNG。少なく・的確にが安全で効果的です。
天然成分の虫除け:エッセンシャルオイルでナチュラル対策
- 「なるべく薬剤は使いたくない」
- 「小さな子どもやペットがいて心配…」
そんなご家庭に人気なのが、精油(エッセンシャルオイル)を使ったナチュラル虫除けです。
なぜなら、合成殺虫剤のように強力に“殺す”のではなく、虫が嫌がる香りで“寄せつけにくくする”のが精油の特徴だからです。
手軽に作れて、香りもよく、日常的な“予防対策”としてとても相性がいい方法です。
虫が嫌がる代表的な精油
精油にはそれぞれ得意分野があります。そのため、目的に合わせて選ぶのがコツです。
レモングラス
- 蚊・アリ対策に定番
- 爽やかで虫除け効果が高い
ユーカリ(シトリオドラ)
- ハエ・蚊に有効
- 市販の虫除けにもよく使われる成分
ペパーミント
- コバエ・アリ・クモ対策に
- スーッとした清涼感
ラベンダー
- ハダニ・蚊対策+リラックス効果も期待できる
ティーツリー
- 防カビ・防菌・防虫に
- 湿気の多い場所にも◎
そして、1種類だけでも効果はありますが、2〜3種類をブレンドすると持続性と幅がアップします。
簡単!虫除けスプレーの基本レシピ
作り方はとてもシンプル。そのため、初めての方でも5分でできます。
用意するもの
- スプレーボトル(遮光タイプがおすすめ)
- 水 … 約100ml
- 無水エタノール … 約10ml
- お好みの精油 … 合計10〜20滴
作り方
- 無水エタノールに精油を入れてよく混ぜる
- 水を加える
- フタを閉めて、よく振る
これで完成です。
※ 精油は水に溶けにくいため、使用前・使用中も毎回よく振るのがポイント。
使い方と注意点
おすすめの使い方
週2〜3回を目安に…
- 鉢のまわり
- ベンチ・物置
- 玄関・網戸・窓のサッシ
など、虫の通り道になりやすい場所にスプレーします。
使用時の注意点(必ずチェック)
- 肌や植物に使う前に、目立たない場所で必ず試す
- 紫外線に反応する精油もあるため、直射日光の当たる時間帯は避ける
- 妊婦さん・赤ちゃん・ペット(特に猫)には使えない精油があるので事前に確認
- 原液を直接使わず、必ず希釈して使用
「強い=安全」ではありません。正しく使ってこそ、ナチュラル対策の良さが活きます。
虫の住処をなくす環境づくり:毎日の掃除と植物管理がカギ
どれだけ駆除しても、虫が住みつける場所が残っていれば、必ずまた増えます。実は、プロが一番重視しているのも「駆除」より「住処をつくらない環境」。
そのため、特別な道具や薬を使わなくても、日々のちょっとした管理だけで、虫は激減します。
庭の清掃習慣をつける
庭に落ちている「何気ないもの」が、虫にとっては最高の住み家&エサ場になってしまいます。そのため、落ち葉・枯れ枝はこまめに掃除するようにしましょう。
とくに、雨のあとに湿りやすい
- 鉢の下
- ウッドデッキのすき間
- 室外機の裏
は、週1回でもいいのでチェックしましょう。
また…
- 手作り堆肥
- 腐葉土の袋
- 肥料の空袋
これらをむき出しにしていると、コバエ・ゴキブリ・ダンゴムシの温床になりがちです。
👉 フタ付きの容器や、防水シートで覆うだけで虫の発生リスクはぐっと下がります。
植物を間引いて風通しを良くする
植物を大切に育てているほど、「詰め込みすぎ」になりがちですが、これは逆効果。
- 風が通らない
- 湿気がこもる
- 葉裏が乾かない
とくに、この状態はアブラムシ・ハダニ・カビ系トラブルの大好物です。
改善ポイント
- 植物同士の間に、手のひら1枚分のすき間を作る
- 壁際・フェンス沿いは特に意識して空間をあける
- 梅雨前や季節の変わり目に軽く剪定して、内部まで光と風を通す
そして、「切りすぎないかな?」と不安な方は、無理せずプロに任せるのも賢い選択です。
👉 剪定のプロに相談したい方はこちら
雑草対策で虫の隠れ場所を減らす
雑草は見た目の問題だけでなく、虫の“基地”そのものになります。
- 小さな虫の隠れ家
- 成虫が卵を産む場所
- 害虫が増える中継地点
そして、こまめに抜くだけでも効果がありますが、ポイントは根ごと取り除くこと。
さらに…
- 防草シート
- マルチング(バークチップ・ワラなど)
を併用すると、雑草+虫の両方を長期的に抑えられます。
自分での対策に限界を感じたら:プロの害虫駆除業者に相談を
これまで紹介してきた方法で、多くの虫トラブルは予防・軽減できます。ただし中には、個人で対処するには危険・負担が大きいケースもあります。
- 刺されたら大ケガにつながる
- 家や庭全体に被害が広がる
- 原因や巣の場所がまったく分からない
こんな状況で無理をすると、ケガ・健康被害・被害の長期化につながることも。そのため、「自分でやらなきゃ」と抱え込まず、早めにプロへ相談することも立派な虫対策です。
プロに依頼したほうがいいケース
次のような状況に当てはまったら、DIYよりプロ対応が安心・安全です。
- スズメバチ・アシナガバチなど、刺傷リスクが高い蜂がいる
- ゴキブリ・シロアリなど、衛生面や建物への被害が心配な害虫が出ている
- 庭全体・家の周囲に被害が広がり、どこから発生しているのか分からない
- 高所の巣撤去や、大量の薬剤散布に不安・抵抗がある
- 忙しくて、継続的な対策が難しい
とくに、蜂やシロアリは、「様子見」が一番危険な害虫です。
プロに依頼するメリット
害虫駆除の専門業者に頼むことで…
- 害虫の正確な特定と原因の特定
- 巣・発生源の根本的な除去
- 危険な作業も安全に対応
- 再発しにくい環境改善アドバイス
など、その場しのぎで終わらない対策が期待できます。結果的に、「何度も市販薬を買い続けるより安かった」というケースも少なくありません。
👉 すぐに来てくれる害虫駆除業者を探すなら
全国対応で相談しやすい【害虫駆除110番】のようなサービスが便利です。
なぜなら…
- 料金の目安が分かりやすい
- 対応エリアが全国
- 緊急対応にも相談しやすい
からです。そのため、まずは「どんな虫か分からない」「見積もりだけ知りたい」という段階でもOK。
まとめ:庭の虫対策の基本は「早期発見・原因除去・安全な対処」
いかがでしたか?
庭の虫対策で大切なのは、強い駆除をすることではなく、増やさない流れを作ること。そのために意識したいのが、「早く気づく → 原因を断つ → 無理のない方法で対処する」この3ステップです。
要点まとめ
- 虫対策は、まず「どんな虫か」を知ることがスタートライン
- 多湿・密植・落ち葉の放置など、虫が増えやすい環境を整えるだけで発生は大きく減らせる
- 天敵・物理的な除去・薬剤を段階的に組み合わせるのが長続きのコツ
- 精油やハーブを使えば、子どもやペットにも配慮したナチュラル対策もできる
- 危険性が高い害虫や被害が広い場合は、無理せずプロに頼るのが安全
今日からできる行動(まずは1つでOK)
- 庭をひと回りして、虫・食害の跡・湿っている場所をチェックする
- 落ち葉、古い鉢、使っていない道具を片づけ、虫の隠れ場所を減らす
- 気になる虫や被害は、スマホで写真を撮って、園芸店や専門サイトで確認
- ナチュラル派の方は、ハーブ1種類+精油スプレー作りから気軽に始めてみる
- 「これは自分では危ないかも」と感じたら、【害虫駆除110番】などの専門業者を比較して相談する
👉 安全で、快適なガーデンライフのために完璧を目指さなくて大丈夫。
そのため、まずは今日できる小さな虫対策をひとつ始めてみませんか?
- 「自分でやる」
- 「プロに任せる」
どちらを選んでも、早めに動くことがいちばんの正解です。そして、気になる方は、まず公式サイトや専門業者のサービス内容をチェックしてみてください。
関連記事:
- 【庭で蜂と遭遇!!】その時の行動と対処法
- 【即日現地に訪問!】蜂の巣駆除のプロフェッショナル「蜂バスター」
- 庭に蜂の巣ができたら?安全な駆除方法と注意点を徹底解説
- 庭の蜂の巣を安全に駆除する究極ガイド
- 【完全ガイド】芝生のアリの巣を業者に駆除してもらう方法
- 【庭を虫から守る革新的方法】コンクリート活用で実現する快適アウトドアライフ
- 【美しい庭を取り戻す!】害虫駆除業者に依頼するメリット
- 【庭の蜂対策】効果的な方法と注意点!
- 庭の虫駆除業者の選び方とおすすめ業者!
- 【庭の害虫駆除法6選!】専門業者から自然派まで
- 【スズメバチ駆除は業者に依頼が安心!】庭の安全対策

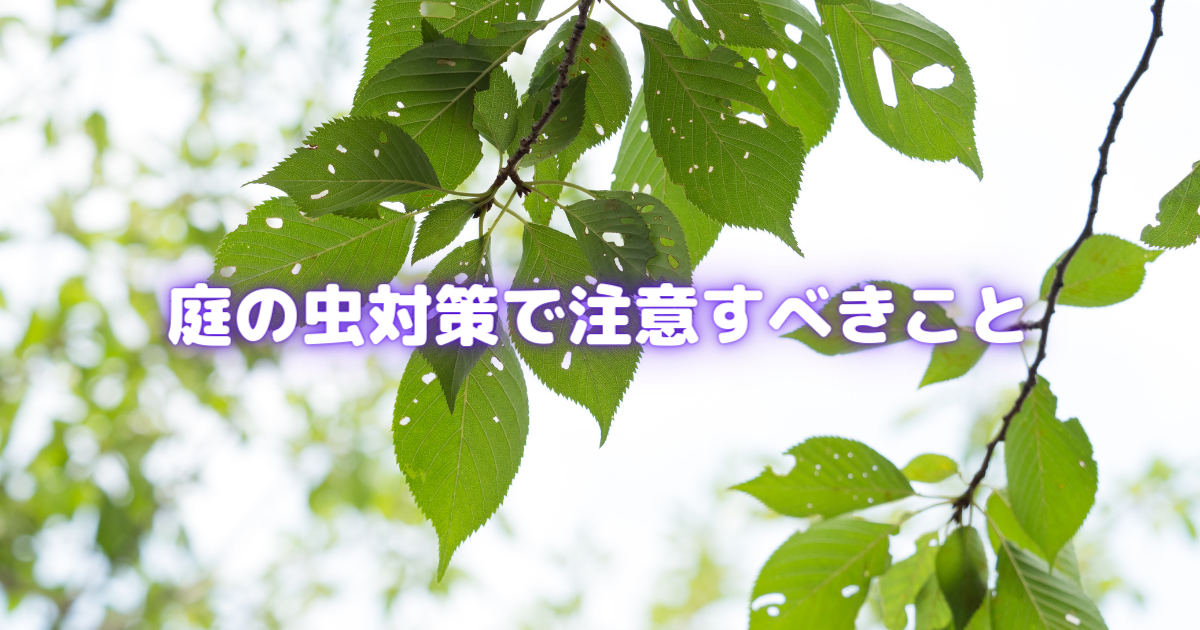


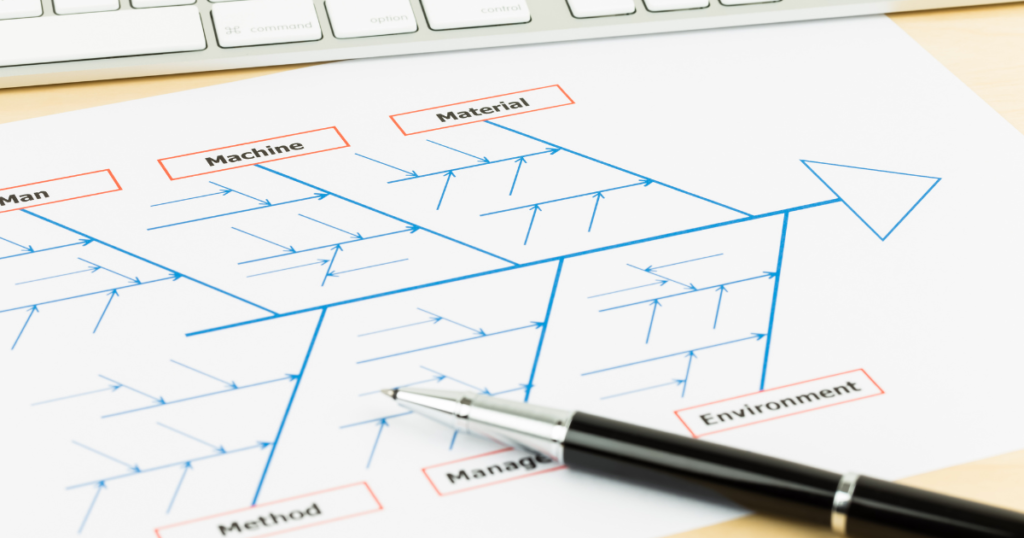












コメント